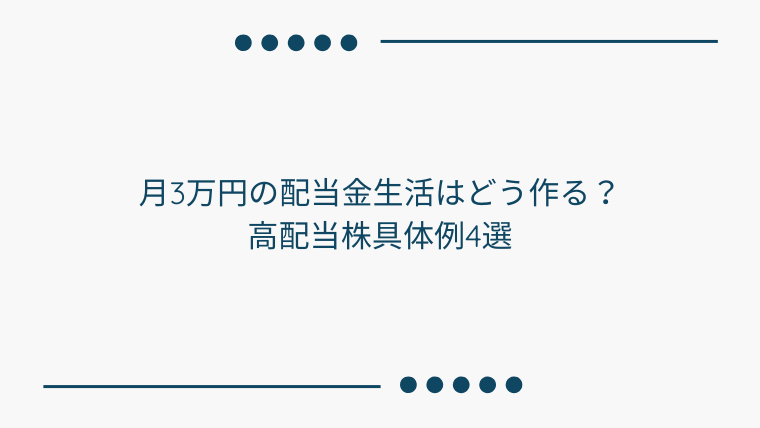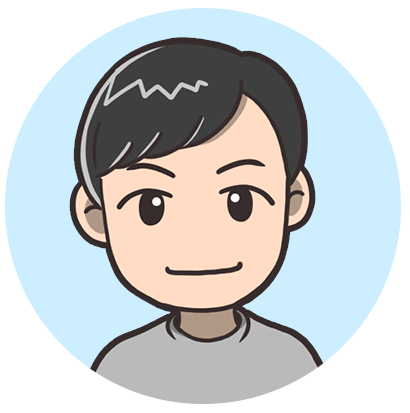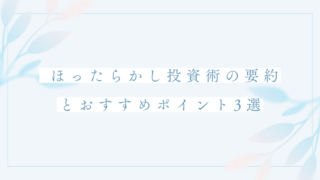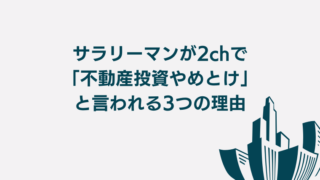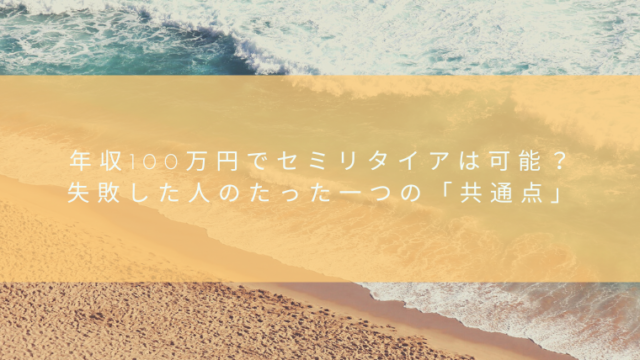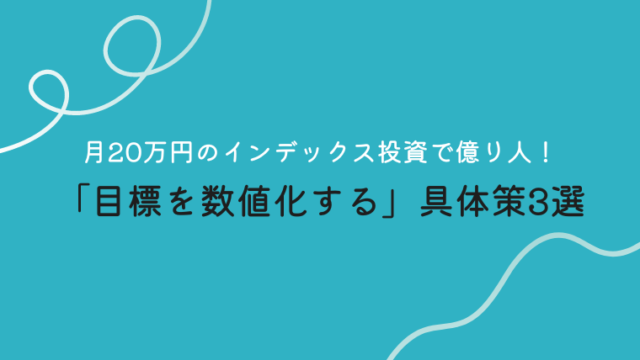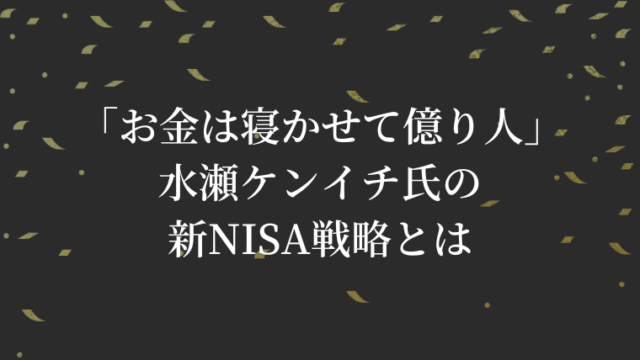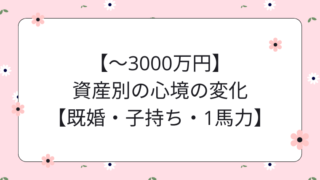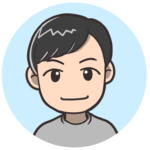ねぇねぇ、パパはインデックス投資以外に、高配当株投資をやっているの?
うん、高配当株はインデックスファンドへの投資とはまた別物で面白いよ。
キャッシュフローを強化したい人には特におすすめだね。
へぇ。
それではおすすめの銘柄や、インデックス投資との違いも含めて教えてください〜!
こんにちは!成長性と配当利回りを両取りするなら、税引後で3%が適正なライン考えているあいろん(@iron_money)です。
今回は「高配当株投資」の醍醐味や、インデックス投資との比較を紹介します。
この記事はこんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
今回の参考書籍「オートモードで月に18.5万円が入ってくる高配当株投資」
パパ、そもそも高配当株投資とはどんな投資法なの?
「高配当株投資」は「インデックス投資」と並んで、長期投資家の間で人気のある手法だよ。
株式を保有しているだけで得られる配当金(インカムゲイン)によって、キャッシュフローを強化する。
上記はわかりやすい「不労所得」となり、生活レベルの向上に繋がります。
高配当株投資は持っていると「配当金」という形で、生活が潤うからとっつきやすいんだね。
一方で、高配当株投資はインデックス投資のような「ほったらかし」とは似て非なる投資です。
高配当株式は、割安度を判断して購入する必要性がある「アクティブ投資」の側面も持ち合わせているんだよね。
そうそう。
上記理由により、本ブログでは「高配当株投資」を取り扱っていなかったんだよね。
でも、非常に参考になる書籍に出会ったので紹介することにしました。
その書籍とは「ど素人サラリーマンが元手5万円でスタートできた!オートモードで月に18.5万円が入ってくる高配当株投資」です。
え…これは…
そるとちゃん、あなたの感想は手にとるようにわかります。
私も思いました(笑)
この書籍は、初見では下記のように感じる人の方が多いでしょう。
上記理由から、あいろんも中々書籍を手に取る機会がありませんでした。
だがしかし!ひょんなことから手にとってみると、内容は下記のような正統派でした。
上記内容は、資産形成期でインデックス投資に比重をおいているパパにも「高配当も面白い」と思わせてくれる内容だったそうです。
本書でも取り上げられていますが、特に下記のような方は一読の価値ありです。
高配当株はインデックス投資より、リスクは高くなりがち。
資産形成の観点から言うと、最適解ではないなど、デメリットもあります。
それを補ってあまりある、「配当金が目に見えて入ってくる」というメリットに魅力を感じるのであれば一考の余地ありです♪
高配当株投資キホンのキ
本書で推奨している「長期配当投資」は、株式の長期保有で「受取配当金額」を増やしている点が特徴です。
しかしながら、「売買のタイミングを考える」「個別株に投資する」点は、自分で判断しなければならない特性があります。
「アクティブ投資」の側面が強いという点は必ず覚えておきましょう。
購入後はほったらかしでOKな「インデックス投資」とは考え方が全然違うんだね。
分散が圧倒的にインデックスファンドに比べて弱いのが、高配当株投資の弱点です。
「長期・積立・分散」が投資の成功確率を高める三大原則だもんね。
分散が弱いのは、致命的だよね。
本書でも取り上げてる、高配当株がもたらした悲劇の代表格として「東京電力」株が挙げられます。
高配当、安定性抜群、とりあえず東京電力の株式を保有しておけば安泰。
東日本大震災前には株式市場に、そんな空気すら市場にはあったと言います。
2011年3月11日時点で2,121円だった東京電力の株価は、震災3ヶ月後の6月9日には148円まで下がりました。
93%減です。
2024年11月時点でも、東京電力の株価は600円程度です。
震災前と後で、全く意味合いの異なる株式になりました。
もし当時に東京電力に集中投資していたら、立ち直れないダメージだね。
どれだけ優良な会社の株式でも、個別である限り、有事の際には暴落がありえる。
この点は、必ず頭に入れておくべきです。
一方で、「毎月のキャッシュフロー(収入)を強化したい」という需要に対して、「定期的に安定した収入が見込める配当金」は素晴らしい選択肢にもなり得ます。
生活の質を上げる、素晴らしい手段です。
東日本大震災前の東京電力株所有者に「株が93%下がるよ」と言っても、誰も信じなかったでしょう。
パパは資産が増えてきて分散を意識するようになり、ポートフォリオに不動産を加えています。
インデックス投資と高配当株投資の違い
前述の通り、インデックス投資と高配当株投資には決定的な違いがあります。
- 高配当株投資→アクティブ運用
- インデックス投資→パッシブ運用
本書では企業分析の指標を、3点に絞ってわかりやすく解説してくれています。
上記は逆説的に考えると、「財務を含めた企業分析」は必須だということです。
PER(株価収益率)
一般的には15倍程度が適正。慣れるまでは10倍以下は割安、15倍を下回れば適正、20倍以上は割高と覚えましょう。
そして分析したデータを基に「これはイケる!」と思った銘柄に、投資します。
個別株の場合、あくまで選定と最終判断は自分で下すスタイルになります。
一方で、インデックスファンドには自分の判断が介入する余地がありません。
一例として、インデックスファンドベンチマーク指標として投資家から信頼を得ているS&P500を見てみましょう。
S&P500は、採用に下記のような基準を設けています。
インデックスファンドは積立だけしておけば「ほったらかしOK」と言われるほど手間がかからないんだよね。
高配当株投資の方が一般的な「株式投資」のイメージに近いね。
高配当株投資もインデックスファンドも同じだと思っていたけど、考え方、選び方、投資の仕方も全然違うんだね〜。
高配当株投資具体例4選
本書では「永久保有したい銘柄」として17銘柄紹介されています。
わたしも17銘柄中、実際に「ここはタイミングを見て買いに動こうかな」と思った優良銘柄が3社ありました。
また、本書には紹介がありませんでしたが指標が優秀な「三菱HCキャピタル」も含めた4社を、今回ご紹介します。
- JT(2914)
- INPEX(1605)
- クボタ(6326)
- 三菱HCキャピタル(8593)
①JT(2914)
- 予想PER(2024/11時点)
- 16.04倍
- 高い利益率を誇るグローバル寡占企業
JT(日本たばこ産業)は、日本で唯一のたばこ製造業者です。
JTの事業には下記のような特性があります。
一方で、タバコ業界は「健康起因に伴う喫煙者数の減少」というメガトレンドも存在しているのは確かです。
2024年には、人気だった株主優待を廃止する発表が行われました。
過渡期であることに、疑いの余地はありません。
直近10年の株価推移は下記の通りです。
| JT株価推移 | |
|---|---|
| 2012年末 | 2,531円 |
| 2015年7月 | 4,813円 |
| 2018年2月 | 3,096円 |
| 2020年3月 | 1,905円 |
| 2022年8月 | 2,293円 |
| 2023年12月 | 3,612円 |
| 2024年2月 | 4,028円 |
| 2024年11月 | 4,219円 |
新NISAでも人気銘柄となり、株価は直近で4,000円台まで上昇しています。
コロナ禍などの有事においても「1900円で下げ止まった」という事実は、覚えておいて損はないでしょう。
一時期は配当利回りが7%あったJTも、今や5%以下です。
個人的には5%の配当利回りは死守したい銘柄ですが、買い増したい場合は単元未満株でコツコツ拾っていくのがおすすめです。
②INPEX(1605)
- 予想PER(2024/11時点)
- 6.88倍
- エネルギー開発と安定供給に責任を果たす国策企業
2021年に社名変更しているため、旧社名の「国際石油開発帝石」に馴染みがある方も多いかもしれません。
国が株式の20%弱を保有、かつ1株でも拒否権を発動できる「黄金株」を保有している国策企業です。
INPEXはその事業ゆえに、現在の株主還元に積極的な姿勢はドラスティックに変更することは考えづらいです。
上記のような考えから、長期配当投資家に非常に注目されているんだね。
直近10年の株価推移は下記の通りです。
| INPEX株価推移 | |
|---|---|
| 2012年末 | 1,153円 |
| 2015年7月 | 1,350円 |
| 2018年2月 | 1,324円 |
| 2020年3月 | 514円 |
| 2022年6月 | 1,784円 |
| 2022年8月 | 1,405円 |
| 2024年3月 | 2,123円 |
| 2024年11月 | 2,031円 |
上記の通り、INPEXの業績は景気に左右(特に原油価格に連動)されます。
値動きが小さいディフェンシブな銘柄と勘違いして、エントリーすると戸惑うこともあるでしょう。
INPEXについては、PERを気にする銘柄ではないです。
現状では株価がやや上がりすぎてしまっている感を感じます。
パパはINPEXの株主優待が最大になる800株まで最終的には買い増し予定です。
現状では1株ずつでコツコツ買い増して、もし暴落がおきたら、一気に購入すると決めているそうです。
③クボタ(6326)
- 予想PER(2024/11時点)
- 9.76倍
- 農業機械世界3位。食料・水・環境に携わる総合インフラ企業
「農機」と呼ばれる特殊かつ安定性の高い分野で、日本を代表する企業です。
グローバル市場でもシェアを持ち、世界第3位につけています。
世界No. 1は米国の「ディア・アンド・カンパニー」という会社で、こちらもパパが個別に株式を保有している優良企業です。
パパ、農機の会社好きだよね。
現状の配当利回りは2.5%程度ですので、高配当株としては低い水準です。
ただし、増配余地もあり10年後には化けている可能性が魅力です。
クボタは水インフラ事業にも携わっており、国内の地中に埋まっている水道管の5割以上がクボタ製品だそうです。
株主還元の配当性向も30%を目標としています。
事業の社会性や必要性から考えて大幅に業績が変動することは考えづらい、と考えて投資しています。
直近10年の株価推移は下記の通りです。
| クボタ株価推移 | |
|---|---|
| 2012年末 | 1,028円 |
| 2015年7月 | 2,123円 |
| 2016年6月 | 1,371円 |
| 2020年3月 | 1,256円 |
| 2022年1月 | 2,606円 |
| 2022年8月 | 2,113円 |
| 2024年2月 | 2,267円 |
| 2024年11月 | 1,961円 |
景気敏感株のため値動きはありますが、本書では「PER15倍、配当利回り2%」程度を目安に買い進めば問題はないという意見があります。
クボタは現状だと、2000円を目安にコツコツ買い増ししていくのが好みです。
④三菱HCキャピタル(8593)
- 予想PER(2024/11時点)
- 10.99倍
- 三菱グループの中核を担うリース会社。2021年4月に三菱UFJリースと日立キャピタルの合併によって国内トップクラス規模。
三菱HCキャピタルはその地味なビジネスモデルゆえ、「知名度と実力値が比例していない」投資妙味銘柄の1つでした。
同社の特徴的な強みは、アセットファイナンスです。
「物」の販売・調達等に関わる金融を事業の主軸とし、純投資は基本的に行なわない。
純投資を生業にする「リース界の王者」オリックスとは、ビジネスモデルからしてスタンスが異なる点も特徴です。
連続増配記録が24年連続になっており、首位の花王を追いかける展開です。
ようやく株価も1000円を超えてきたものの、まだPER的に割高感がありません。
直近10年の株価推移は下記の通りです。
| 三菱HCキャピタル株価推移 | |
|---|---|
| 2012年末 | 350円 |
| 2015年7月 | 675円 |
| 2016年6月 | 419円 |
| 2020年3月 | 463円 |
| 2022年1月 | 609円 |
| 2022年8月 | 666円 |
| 2024年2月 | 1,053円 |
| 2024年11月 | 1,057円 |
高配当株投資でコツコツ買い進めるなら、三菱HCキャピタルは有力候補です。
株価的にも買いやすく、向こう20年間の増配が期待できる財務面。
隙が少ない会社だね。
パパは「三菱HCキャピタルは増配を続けると読んでいる。
10年スパンでコツコツタイミングで買い増しする」とよく言っています。
辺りの判断が個別株の醍醐味だそうです(笑)
ポートフォリオ(あいろんの一例)
今回ご紹介した4銘柄は、大別すると下記のように仕分けが出来ます。
上記より、ディフェンシブは「コツコツ買い」景気敏感株は「タイミングでロット買い」が私の基本スタンスです。
ちなみにパパは上記4銘柄であれば、下記のような割合を目指して保有するそうです♪
- JT(35%)
- 三菱HCキャピタル(35%)
- INPEX(20%)
- クボタ(10%)
上記で配当利回り+増配も加味しながら新NISAの成長投資枠を活用すると仮定した場合、3年程度で月3万円の配当金が見えてきます。
パパ的には上記は相当吟味した末の個別銘柄なので、分散は多少弱いけど大崩れはしないと踏んでいるそうだよ。
個別株式で安定したキャッシュフローを得たい場合には、参考にしてみてください。
ラップアップ
今回は「高配当株投資」の醍醐味やインデックス投資との比較を紹介しました。
企業を分析して、将来を信じ、家計のキャッシュフローも良くなる。
株式投資好きにはたまりません。
「インデックス投資だけだと少し物足りない」
「リスクを極力抑えて個別株に投資してみたい」
上記の方は是非一度、トライしてみることをおすすめします。
最後に一言。
高配当株投資は株価が上がったら嬉しいし、下がったら配当利回りが高まって「買いどき」と考えられるので精神的にも続けやすいですよ。
それではまた!