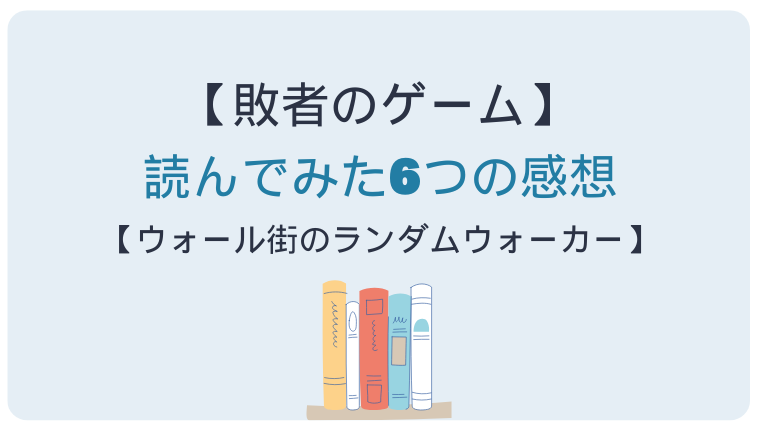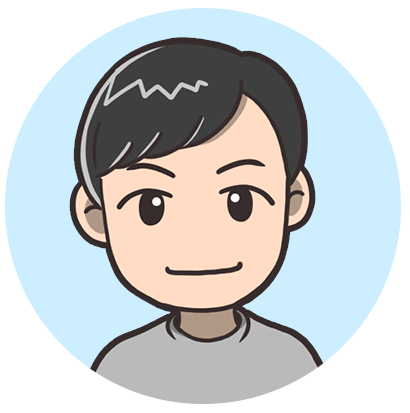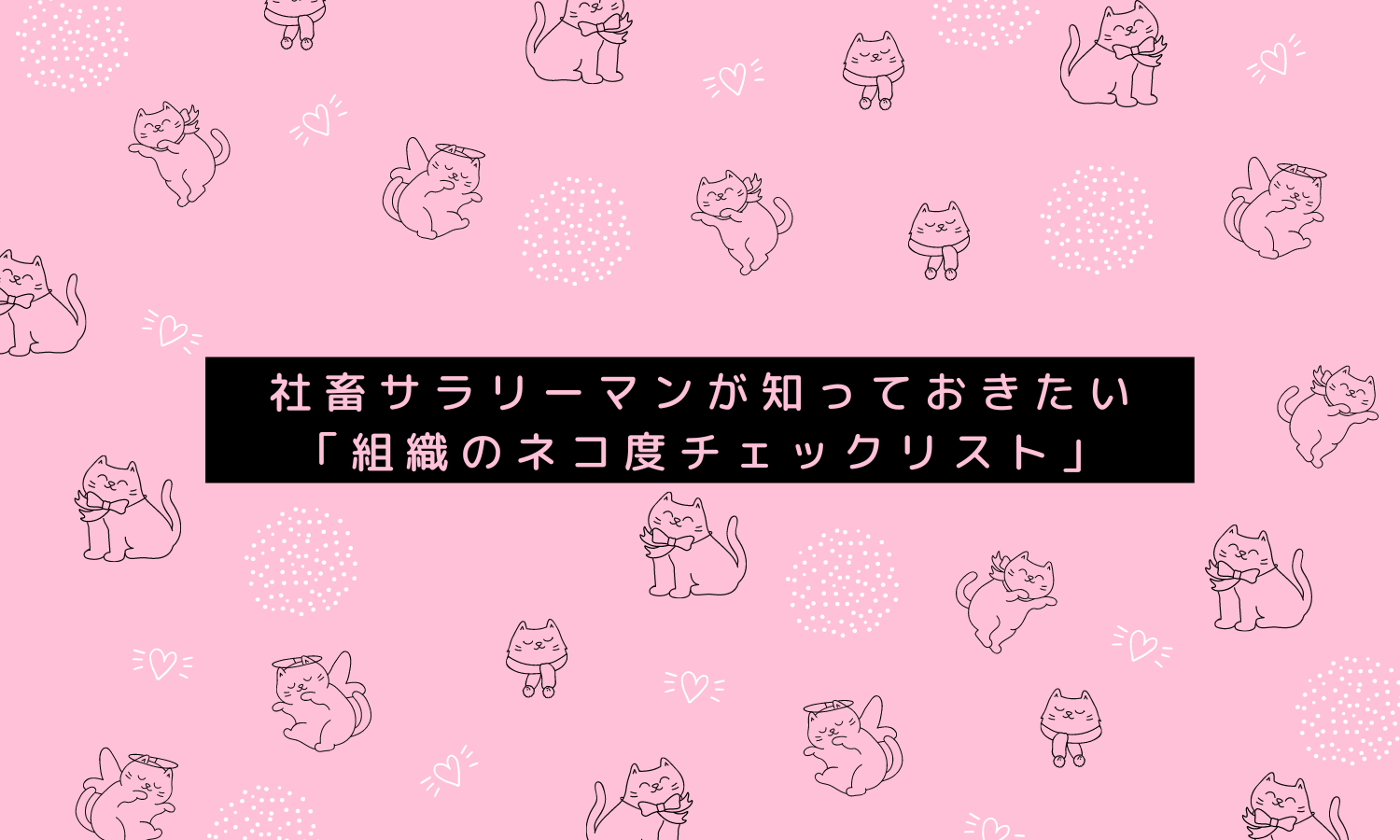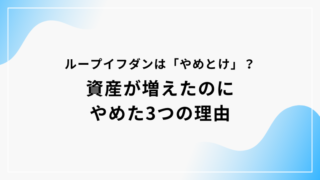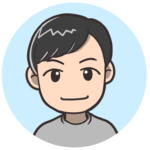ねぇパパ、パパは投資系書籍の記事を書いているのに、「敗者のゲーム」はまだだよね?
(ぎくっ)…実は昔に読んだんだけど、あんまり内容覚えてないから第8版が発売されたタイミングで読み直したばかりなんだよね。
遅い!
あと、「ウォール街のランダムウォーカーとどっちを読めば良いかわからん」という声があるからそれにも言及するように!
はい、すみません…すぐにまとめます。
こんにちは!関連書籍を数百冊読んだ結果「敗者のゲーム」と「ウォール街のランダムウォーカー」の2冊だけ読んでおけば間違いないと思っているあいろん(![]() @iron_money)です。
@iron_money)です。
今回は株式投資のバイブル、世界で100万部を超える超ベストセラー「敗者のゲーム」を「ウォール街のランダムウォーカー」と比較しながら解説していきます。
この記事は、こんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
今回の参考書籍①「敗者のゲーム」
「敗者のゲーム」は1985年に初版が発行され、36年の時を経て2022年に第8版が出版されました。超ベストセラー書籍です。
パパ的に「資産形成で役立つ本を1冊だけ選ぶ」という条件だったら「敗者のゲーム」を選ぶそうです。
投資本を数百冊以上読んでる、パパが選んだNo. 1なんだね♪
著者は米国公認証券アナリスト協会の会長をはじめ、資産運用界隈に大きい影響を及ぼす重鎮チャールズ・エリス氏です。
後述して紹介するバートン・マルキール氏からも下記のような賛辞を受けています。
「エリスはテニスの試合を例に取り、アマチュアは相手に負けるのではなく、自分のミスで自滅することが多い、と述べる。アマチュア同士で試合をすると、ミスが少ない方が勝つ。投資も同じである」
インデックス投資は「アマチュアのテニス」と同じだという比喩表現は秀逸すぎてしびれます。
また、本書の特筆すべき点は「時代に合わせて内容が更新される」点です。
例として、最新版である第8版では「退職後の債券投資」について再考すべきだと述べています。
初版が発行された36年前とは債券や株式に対する手数料や商品ラインナップが変化しているもんね。
時宜にかなった、エリス氏のアドバイスを簡単に入手できる。
「敗者のゲーム」の最大の魅力であり、投資の勝者になれる具体的な思考がギュッと詰まった良書です。
今回の参考書籍②:「ウォール街のランダムウォーカー」
「ウォール街のランダムウォーカー」は1973年に初版が出版されました。
2025年現在、第13版が最新です。
本書の特筆すべきポイントは、「アクティブ投資はなぜインデックス投資に勝てないのか」を理詰めで腹落ちできるところです。
著者のバートン・マルキール氏はプリンストン大学を代表する経済学者であり、金融のプロです。
本書はタイトルにもある通り、金融のプロが市場は「ランダム・ウォーク」だと断言します。
株式相場には規則性があるようで全くない。という衝撃的なテーマなんだよね…!
本書は不確実性の多すぎる市場において、低手数料のインデックスファンドこそが投資の最適解になり得ると結論づけています。そして上記に対して膨大な根拠内容を費やしています。
マルキール氏は、本書の中で下記のように語っています。
「本書に副題をつけるとすれば、ゆっくりと、しかし確実に金持ちになる本だろう」
ウォーレン・バフェットさんと同じこと言ってるね。
投資に絶対などありえない。自分の想像通りに世界が動くなどありえない。
ただし時間と前提さえ間違えなければ、「お金を増やす」確率が高い方法は存在する。
「当たり前」をいかに誰も実践できていないか、マルキール氏は熱を込めた文章で啓蒙してくれます。
両書の共通点について
- 共通点①投資の最適解はインデックスファンドである
- 共通点②時間軸を10年超の長期目線で見る
- 共通点③「リスク」と「リターン」の本質的思考
両書の概要紹介を終えたところで、あなたが気になる点は下記だと思います。
「何が違うのか?」
「どっちを読めば良いのか?」
「難しそうだけど大丈夫か?」
今回は①両書の共通点②両書の相違点について下記で解説するよ。
どちらの書籍も違いはあるけど、インデックス投資で資産形成したい人にとっては必読です。
何度でも読み返したくなる最高のエンターテイメント書籍です。
共通点①投資の最適解はインデックスファンドである
「敗者のゲーム」著者のチャールズ・エリス氏は本書で下記の通り述べています。
「投資で長期的に成功したいなら、答えはシンプルだ。実行が簡単なインデックス・ファンドを買うこと。平均なんて嫌だ、市場に勝ちたいと思うかもしれない。しかし、個人がプロに勝とうとするなんて100年早い。」
これは必ず覚えておきたい真実です。
インデックス投資こそが投資界における「ドリームチーム」であり、手数料が低く、税金が安く、実行コストが下げられると主張しています。
「ウォール街のランダムウォーカー」においては、初版発行の1973年に著者のバートン・マルキール氏が下記のように主張していました。
「時価総額ベースで米国の4分の3をカバーしているS&P500に投資できれば、長期的にはほとんどの投資のプロを上回る。この指数に含まれるすべての銘柄をそっくりそのまま購入することが、株式投資を考えた時の簡単で優れた方法の一つである」
じつは1973年時点ではまだインデックスファンドが発売されていなかったそうです。
本書のアイデアが注目され、1976年に一般投資家を対象とした最初のインデックス・ファンドが売り出されたそうです。
両書は時代背景や論法に多少の違いはあれど、結論は全く同じ場所に着地しています。
なぜ、ここまでインデックス・ファンドが世界中で話題になるのか。評価が高いのか。
両書を読んで、心からインデックスファンドのもたらすリターンについて考えることが大事です。
多少の下落にうろたえる事もなくなり、安定した長期的資産運用が見込めるようになります。
共通点②時間軸を10年超の長期目線で見る
「敗者のゲーム」においては大部分を「時間が教える投資の魅力」として力説しています。
運用期間が長ければ長いほど、ポートフォリオ全体の収益率は平均収益率に近づく。
個別証券の収益率の差は、期間が長くなるほど広がっていく。
運用期間が十分長ければ、短期では大きなリスクと見える運用手法を、不安なく取り入れることができる。
測定期間が長くなるにつれ、個々の年間収益率の違いが互いに打ち消され、平均収益率に近づいていくということになります。
一方、ウォール街のランダムウォーカーでも投資期間については最重要項目レベルで文章量多めに記載されています。
ウォール街のランダムウォーカーで使用されている「株式投資の投資期間と平均リターンのちらばり方」のグラフはあまりにも有名です。
未だに語り継がれる伝説のグラフなので、見たことがあるという方も多いでしょう。
大体15年以上の期間でみると、いつからはじめてもS&P500は平均リターンがプラスになるってやつだよね。
「投資期間25年以上で、配当を全額再投資し、ドルコスト平均法に従って追加投資を続けること」
上記によって、株式のリターンは債券や預金保険の対象となる貯蓄よりも高いリターンになります。
共通点③「リスク」と「リターン」の本質的思考
敗者のゲーム内で、ミスターマーケット(株式市場)の本質についてチャールズ・エリス氏は下記のように述べています。
「毎日の、また月ごとや年ごとのリターンに法則性は見られないが、全くないわけではない」
「ミスターマーケットの放埓な動きの影には、平均への回帰という明らかな傾向があるからだ」
上記については、バートン・マルキール氏の考えとも明らかに一致しています。
リスクもリターンも統計学に落とし込めば、恐るるに足らずと言っているわけですね。
更に「ウォール街のランダムウォーカー」内で、リスク許容度について下記のような会話があります。
「保有株の見通しが心配で夜も眠れず、いったいどうすればいいのかね」
「安眠できる水準まで株のウェイトを下げるんだ」
「どの投資家も自分にとって最適な(期待)リターンとリスクのバランスが、どこにあるかを選ばなければならない」
「この安眠水準だけは、本人にしかわからない」
上記は資産運用において真理中の真理です。
本書の発言の重みは他書籍を圧倒しています。
「あなたの安眠水準を決めることこそ、すべての投資プロセスの出発点なのだ」
リスクとリターンの本質的思考を得られるのも、名著として語り継がれている両書の共通点です。
両書の相違点について
- 相違点①グラフ・図の挿入
- 相違点②結論に導く切り口「サル」と「テニス」
- 相違点③「市場に居続ける」意味
前述の通り、「敗者のゲーム」「ウォール街のランダムウォーカー」は投資の共通項が多く語られています。
しかしながら、内容や切り口が異なる点もあります。
主だった相違点を3点紹介します
相違点①グラフ・図の挿入
「ウォール街のランダムウォーカー」はとにかくグラフや図の入れ方が秀逸です。
膨大な研究結果に基づいた結論を、わかりやすく図やグラフでまとめています。
視覚的にもわかりやすい♪
前述の「株式投資の投資期間と年平均リターンのちらばり方」は1950年〜2017年の統計学をたった1スライドで直感的に理解できます♪
また、下記のような図も本書には挿入されています。
ぶっちゃけ「ウォール街のランダムウォーカー」に関しては、文章を読まなくてもグラフや図を見るだけで十分に購入する価値がある書籍です(笑)
「敗者のゲーム」でも同様に図やグラフ、挿絵は入っているけどね。
特に図が秀逸で役に立つのはランダムウォーカーだとパパは思っているよ。
相違点②結論に導く切り口「サル」と「テニス」
「比喩を使って説明すると、物事はわかりやすくなる。すぐれた比喩は、私たちの考え方や市場をも動かす」
上記はバートン・マルキール氏が「敗者のゲーム」に寄せた序文です。
前述の敗者のゲーム紹介でも触れた通り、チャールズ・エリス氏は株式市場をテニスの試合に見立てています。
株式相場はプロテニスのようにドロップショットや力強いサーブで点を取って勝つものではない。
この考え方は、わたしの投資の軸になっています。
ミスが少ない方が勝つのだから、淡々とボールを返し、相手のミスを待つのが最良の選択と説く。
それが「敗者のゲーム」の特徴であり、パパの投資哲学なんです。
一方の「ウォール街のランダムウォーカー」は、ランダムウォークをわかりやすくダーツに喩えた比喩があります。
「サルがダーツを投げて選んだ株の運用成績と、ファンドマネージャーの運用成績は同じである」
上記は「ランダム・ウォーク」を例える名言として、著書の要約としても使われることの多い文言です。
ファンドマネージャーを全否定したということで、色んな議論が起きたんだよね(笑)
本書によるとバートン・マルキール氏は実際に学生たちに架空の株式を作らせ、下記のような実験をしたそうです。
その時の、チャーティストの反応は下記です。
「これは、なんていう銘柄だい。今すぐ買いだ!こいつは古典的なパターンだ。来週中に少なくとも15ポイントはいけるはずだ」
これは面白いね。適当に作ったチャートでも的外れな分析ができちゃうんだね(笑)
そして上記チャートは架空とタネあかしをした時、チャーティストは怒ってしまったそうです。
マルキール氏がその後「チャーティストという連中は、ユーモアのセンスがない」と勝手にテストしといてぶった斬るシーンは中々秀逸です(笑)
上記のような「比喩表現」について、両書とも巧みに使っています。
例えも切り口も違うので、同じような結論でも全く違う読み物として楽しめます。
相違点③「市場に居続ける」意味
前述の通り、全体的なグラフや図に関しては「ウォール街のランダムウォーカー」に軍配があがると述べました。
しかしながら、「敗者のゲーム」にはウォール街のランダムウォーカーに記載されていない強烈なパンチラインがあります。それは「市場に居続けた方が良い」という結論をハッキリと決定づけてくれる内容です。
敗者のゲームには、S&P500の36年間のデータの中で、ベストデーを逃した時の株式のリターンに与える影響グラフが出てきます。
上記の要旨は下記の通りです。
- 最も上昇した10日を逃すだけで、リターンの平均水準は11.4%から9.2%へと低下する
- 更に20日間ベストを逃すと、7.7%に低下する
- 20年間の株のトータルリターンのすべてはベスト「35日間」に達成されている
- 上記の35日間は、集計した5000日の取引日の1%にもならない
チャールズ・エリス氏は上記をもとに結論づけます。
「もし私たちに、それがどの月かを見分けることができれば、利益は計り知れない。しかし、そんなことは不可能だ」
「現時点でわかることは、たった2日間を逃したら、20年間にわたって蓄積される利益のすべてを失ってしまうということだ」
これはとんでもないデータです。
タイミング投資がいかに難しいかを示しています。
そしてチャールズ・エリス氏は後世に残る名言で締めくくります。
投資家は、「稲妻が輝く瞬間」に市場に居合わせなければならない。
上記のエリス氏の文言を読んだ瞬間、鳥肌が立ちました。
なぜなら長年の悩みが一瞬にして解決したのを感じたからです。
自分の勝手な判断で「底だ」「天井だ」と思ったタイミングが、もし別だったら?そしてその後に本物の稲妻が届いたら?
上記を考えると、「市場に居続けない」ことがいかに愚かがよく分かります。
「インデックス投資はタイミングを読まなくて良い」という真意はこれだったのか…!と震撼したものです。
上記は「ウォール街のランダムウォーカー」との比較相違点というよりは、「敗者のゲーム」の唯一無二の痺れるポイントと言えます。
パパ的には、この「稲妻」の説明だけでもチャールズ・エリス氏の思考と比喩を存分に味わえる極上のエンターテイメントであり、敗者のゲームが絶対に買いである強い理由と考えています。
結論:難しい事は書いてない
前述の通り、投資において「ウォール街のランダムウォーカー」「敗者のゲーム」は他の追随を許さない良書として君臨し続けています。
結論としてまとめると、下記になります。
- お金は投資すると増えるというデータがある
- データを見るとインデックスファンドが良い
- その他にも色んな考え方があるから、それも調べてみたけどやっぱりインデックスファンドが良い
書籍の内容をざっくり書くと、上記のような話くらいしかしていません(笑)
しかしながら、投資をしていると必ず訪れる「不安」や「欲望」に悩んだ時に立ち戻れる根拠が膨大な量記載されています。
「ステージや環境の変化が起きたごとに、何度でも読み返したくなる」
これこそが何よりも両書の価値であり、他書籍へのアドバンテージでしょう。
ラップアップ
今回は投資界の超ベストセラー「敗者のゲーム」を「ウォール街のランダムウォーカー」と比較しながら解説していきました。
刺激的な内容も嫌いではありませんが、やはりインデックス投資の素晴らしさに立ち戻るにはこの二冊がベストです。
食わず嫌いの方も、見える世界線が変わるので是非お試しあれ。
最後に一言。
新NISAの投資対象を選ぶ前に、2冊とも読んでおくと良いですよ♪
それではまた!