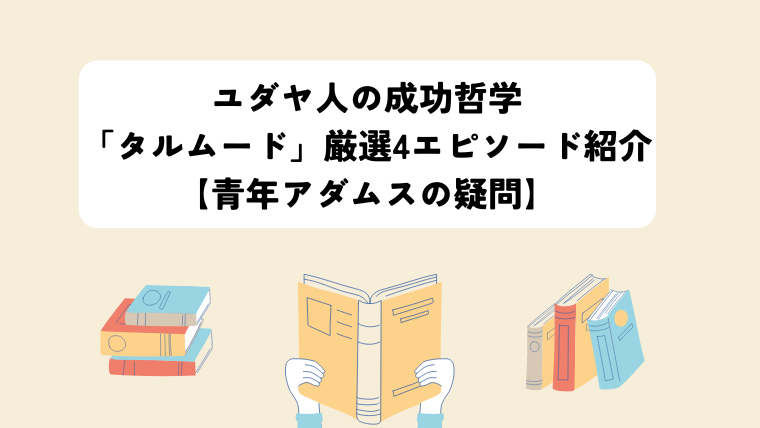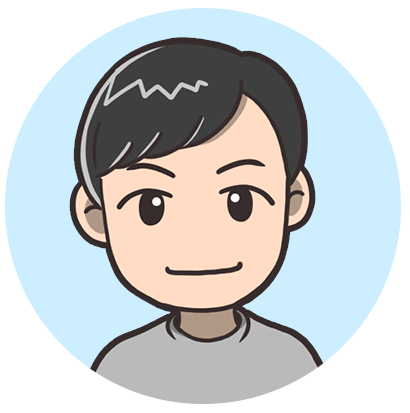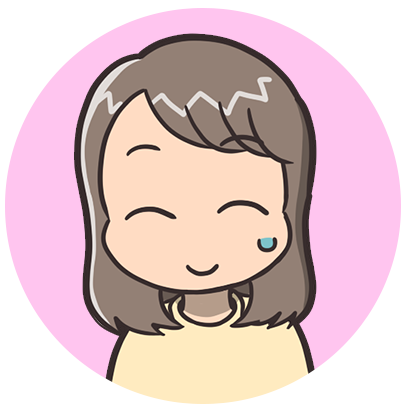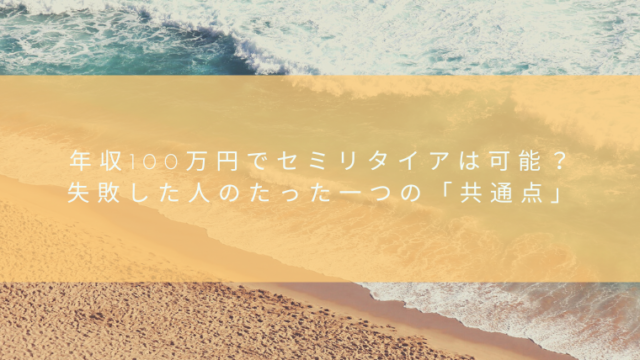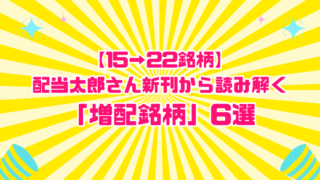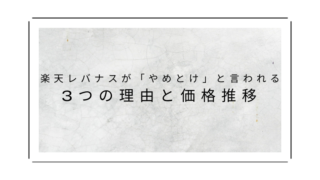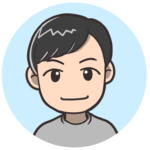パパ、今日も寝る前に「タルムード」から青年アダムスのお話を読んで聞かせて欲しいな♪
前回は「魔法のザクロ」という小話を読んだよね。
今日は青年アダムスの話を読もうか。
魔法のザクロの格言は「ノーペイン・ノーゲイン」だよね!
今日のお話も楽しみ♪
そるとちゃん、よかったね。
タルムードは楽しく人生の本質を学べるから子どもへの読み聞かせにも最適だね。
こんにちは!タルムードは日本の義務教育にした方が良いと考えているあいろん(@iron_money)です。
今回はユダヤ人の思考法「タルムード」の面白いかつためになるエピソードを紹介します。
この記事は、こんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
ユダヤ人の思考法とタルムード
今回の参考書籍「タルムード金言集」はユダヤ人の成功哲学、タルムードを題材にしています。
とても読みやすく、大人でも子どもでも楽しめます。面白い格言や小話と共に紹介している本です。
本書は、下記のような書き出しからスタートします。
ユダヤ人は世界で起こる不幸を一番先に予知し、一番最後に幸福を知る人々である
石角完爾著 集英社 (2012/4/20)
どういうこと?
難しくてよくわからないなぁ。
確かに哲学的すぎて良くわからないよね(笑)
キーワードは「リスクコントロール」だよ。
本書には、下記の記載があります。
「僕ならこうする」
「私ならこんな方法を取る」
工夫やアイデアを子供の頃から議論するクセがついているため、ユダヤ人は「リスクコントロール」を無意識に学べます。
楽しみながら議論や想像を通じて思考力を膨らませる。
ユダヤ人にノーベル賞受賞者が多いのも納得です。
そして議論の元となる説話が掲載されているのが「タルムード」です。
ユダヤの格言において、こんな言葉があります。
この世には人を傷つけるものが三つある。
- 悩み
- いさかい
- 空の財布
三つのうち、空の財布が最も人を傷つける。
「お金がないのは不幸である」と言いきっているんだね、中々極端な考え方だね。
この格言にユダヤ人の思考法が集約されている気がします。
「心の平穏は財布次第」
「お金が人生における扉を開ける大切な鍵」
本書では、ユダヤ人のお金に対する優先度が記載されています。
パパはユダヤ人のお金の考え方について、概ね同意しているそうです。
日本の金融教育は「お金を稼ぐ人は悪い事をしている」「汗水垂らして稼いだお金が美徳」のようなミスリードが多い。
見習うべき視点だ!と考えているそうだよ。
私はタルムードを知り、なぜ人口の少ないユダヤ人が様々な分野で優秀なリーダーが生まれ続けるか理解できた気がします。
ユダヤ人の常に物事を考え続けるハイレベルな「思考力」のベースは、タルムードを通じて受け継がれているんだね。
タルムード金言集おすすめの読み方
さて、ここまで本書の内容について「見習うべき部分」を中心に解説しました。
しかしながら本書を読んでみて、「見習う必要ない部分」も含まれているとあいろんは考えます。
書籍の内容は良くまとまっている反面、日本人ディスりがひどいと感じました。
「タルムード金言集」は、日系ユダヤ人の石角完爾氏が執筆しています。
石角完爾氏は、ユダヤ人の中でも「ウルトラオーソドックス派」という宗派に属しているそうです。
ウルトラオーソドックス派は「必要以上の贅沢はせず、つつましく暮らすためのルールが細かい」宗派です。
書籍内でも下記のような論法を多用しています。
「ユダヤの考え方は〜」
対比
「日本はだからダメなんだ〜」
改宗して上記の宗派に属しているため、自分の生き方に誇りがあるのでしょう。
多少しょうがない気もしますが、大抵の日本人読者は「日本をディスりすぎだろ」と思うこと請け合いの文章です。
パパは読後に「著者の主観がひどい。面白いのに残念」とよく言っていたよね。
上記より、本書のおすすめの読み方は下記になります。
- 著者の説明部分は飛ばす、もしくは読み流す
- タルムード説話部分のみを全て読み込む
- 特に面白いと思った話だけを参考教訓にする
上記だけでも十分に面白く読み進められます。
本書はヘブライ語で書かれているタルムードから内容の抜粋や翻訳して、日本向けに書籍化してくれています。
それだけでも価値はあります。
無駄な日本ディスりに対しては反応せず、タメになる部分だけを読み込んでいくのがおすすめだね♪
タルムードおすすめ小話4選
さて、いよいよタルムードのエピソード説話(小話)について厳選4話を紹介するよ♪
因みに書籍内では30程度のお話が紹介されています。
どれも面白いので是非書籍をチェックしてみて下さい。
魔法のザクロ
おすすめ度:☆☆☆

物語のあらすじ
あるところに仲良しの3人兄弟が住んでいた。
3人はそれぞれ修行に出て、10年後に落ち合うことにした。
落ち合う時には、それぞれが旅で見つけたもっとも不思議なものを持ち寄る事にした。
そこで3人は10年後、それぞれの「もっとも不思議なもの」を持ち帰って合流した。
その3人は持ち帰ったものを見せ合い、その不思議な力でお姫様の重病を治す。
3人の内、誰かがお姫様と結婚する事になるのだが…
教訓
このお話、最終的にお姫様は末っ子と結婚します。
3兄弟はみんなお姫様と結婚したくて自分が見つけた「不思議なもの」でお姫様を治そうとします。
その結果、お姫様は共通の質問を3兄弟に投げかけました。
そして、その答えを聞いてから末っ子と結婚することにしました。
お姫様の質問は「私を助けようとしたときに何を失いましたか?」なんだよね。
末っ子だけはお姫様のために使った「不思議なもの」を半分失ったんだよね。
そう、つまり末っ子はお姫様のために「リスクを取った」わけだよね。
お姫様はそこに心打たれました。
「リスクは取りたくないけど、リターンは欲しい」
「月利数十%、元本保証の詐欺事件」
上記のような言葉が聞こえてくる時点で、日本人は大半がノーペイン・ノーゲインの本質を理解していません。
少しでも多くの人がタルムードに触れれば、上記のような詐欺事件などもなくなるでしょう。
「魔法のザクロ」は義務教育にした方が良いと思うくらい、本質をついているお話だと感心しました。
また、「捨てる痛みが先」という点もしっくりきます。
リスクを負わずに利益を先取りしようとする人間に、道は開けないという点も納得感があります。
「損得勘定でしか動かない人に魅力を感じない」とずっと思っていたのですが、その理由がわかった小話でした。
なんとなく感覚的に理解できるから、子どもでもおすすめです♪
ナポレオンとニシンの話
おすすめ度:☆☆
物語のあらすじ
ナポレオンがヨーロッパを征服したときに、それぞれの国の協力者に褒美を取らせることになった。
頼んだものは、下記の通りである。
- フランス人は「ワイン畑とワイン工場」
- ドイツ人は「麦畑とビール工場」
- イタリア人は「小麦畑とパスタ工場」
- ユダヤ人は「ニシンを二匹だけ欲しい」
ユダヤ人の願いはその場ですぐに叶えられ、ニシンをもらって帰っていった。
他国の人間は「せっかく褒美をもらえるのにニシンを二匹だけとは頭が悪い」とユダヤ人を嘲笑していた。
その後、ナポレオンはすぐに没落した。
他国の褒美の約束が叶うことはなく、結果的に願いが叶ったのはユダヤ人だけだった。
教訓
とても痛快で考えさせられるエピソードです。
「欲張らず、すぐ叶えられる小さなことから着実に実践していこう」という教訓なんだね。
油断するとユダヤ人以外のように大きくリターンを取りたくなってしまうものだよね。
ニシンを二匹だけ、という辺りのラインも含めて絶妙で好きです(笑)
他の国の人たちはみんな、欲張りすぎて結局何も手に入れられなかったんだね。
金融用語の「流動性リスク」を直感的に子どもでもわかるようにした感じのお話だね。
面白い!
金の冠をかぶった雀
おすすめ度:☆☆☆

物語のあらすじ
ユダヤのもっとも有名な王「ソロモン王」は鷲に乗って空を飛び、領国内の隅々まで視察して回っていた。
ある日、ソロモン王が鷲の背から落ちそうになったところを雀たちが落ちないように支えた。
雀に大変感謝したソロモン王は、「なんでも欲しいものをあげる」と雀たちに言った。
雀たちは巣に帰って、何をもらうか大激論した。
「いつでも身を隠せるブドウ畑」
「いつでも水が飲める池」
「いつでも食べ物に困らないように落穂をまいてもらう」
雀たちは結局、「王様と同じ金の冠」を全員にもらうことにした。
すると今まで見向きもされなかった雀たちは、金の冠をかぶっているために全国で猟師たちに狩られるようになってしまった。
最後の5羽になるまで雀たちは撃ち殺され、命からがらソロモン王の元にたどり着いた雀は言った。
「私たちが間違っていました。金の冠はもういりません」
教訓
ユダヤの教えでは、「弱者は安全に少しずつ利益を何世代にも渡って積み重ねる」ことを説いているそうです。
「弱者が金持ちのように振る舞うと強者に狙われる」
上記は真理です。
この物語で重要なのは「金持ちになる前にこの考え方を知っておかないと取り返しがつかないことになる」という点でしょう。
お話の中では雀たちはなんとか5羽生き残りましたが、その他の雀たちは全員殺されてしまったのですから…
「お金持ちほど質素で地味な生活をしている」と聞いたことがあるけど、きっとこの教訓を知っているんだね。
「富は何世代にも渡って紡いでいくもの」という感覚はしっくり来ます。
富裕層は時間をかけて富や財産を築いているものです。
「金の冠」を被ったって、リスクが増えるだけでいいことなんか何もないんだよね。
「金の冠=見栄」と考えることが出来そうなお話だよね。
青年アダムスの疑問
おすすめ度:☆☆☆
物語のあらすじ
アダムスはユダヤ教の勉強の中で、解決できない疑問にぶち当たった。
「なぜ神は良い人に不幸を与え、悪い人に幸せを与えるのか?」
アダムスは町を訪れた預言者、エリジャにお願いして旅に連れて行ってもらうことにした。
エリジャはアダムスを連れて行く代わりに「なぜだ」と質問してはならないと、条件をつけた。
旅の1日目
2人は貧しい夫婦の家に泊まった。
ご馳走をふるまってくれた。
翌朝、夫婦のたった一つの財産の乳牛は突然死んでしまった。
旅の2日目
大金持ちで強欲な商人の家に泊まった。
食事もふるまわれず、軒下で寝ろと冷たくあしらわれた。
翌朝立ち去る時、エリジャは嵐のために倒れていた木を元の状態に戻した。
旅の3日目
裕福で欲深い信者ばかりのシナゴーグに泊まった。
信者たちは2人に貧しい食事を与えた。
エリジャは立ち去る時に「あなた方全員が立派なリーダーになるよう神は祝福されるだろう」と祈りを捧げた。
旅の4日目
貧しい村のシナゴーグに泊まった。
2人を手厚くもてなしてくれた。
エリジャは立ち去る時に「あなた方の内のたった1人が立派な指導者になるように神は祝福されるであろう」と言って祈った。
ここで、アダムスは我慢できなくなり、禁じられた質問、「なぜ」をエリジャにおこなった。
エリジャは約束を破ったアダムスの前から立ち去った。
しかし、立ち去る前に真実を教えてくれた。
1日目の乳牛が死んだ時、同じ時刻にあの主婦が死ぬ予定になっていた。
2日目に庭の木を植え直したのは、木の根本に埋まっていた5万枚の金貨を強欲な主人に見つからないようにしたからだった。
3日目のシナゴーグでは、全員がリーダーになって意見がまとまらないようにあえて全員を祝福した。
4日目のシナゴーグでは、1人の指導者により運営が適切に行われ村が栄えるように仕向けていた。
教訓
この話の主眼は下記です。
「神ならどう考えるか」
「物事には色んな側面がある」
上記により、人間が見落としがちな事実を認識させてくれます。
この教訓が特に際立って活きるのは、悲しい出来事が起きた時です。
出来事を神の目線から考えた時、感情から離れて俯瞰的に捉えることの大事さを説いているね。
マインドセットの重要さがわかる、タメになるお話だね。
他に比べると少し難しい話だけど、深みがあるね♪
ラップアップ
今回はユダヤ人の思考法「タルムード」について記事にしました。
特にパパが勉強になった4つを紹介しましたが、その他にもたくさんのお話が載っています♪
興味のある方は是非ご覧になってみることをおすすめします。
最後に一言。
タルムードはお子さんへの読み聞かせもおすすめですよ♪
それではまた!