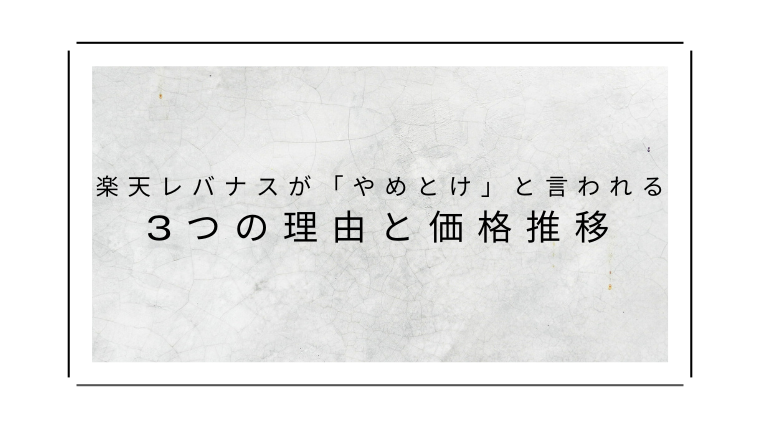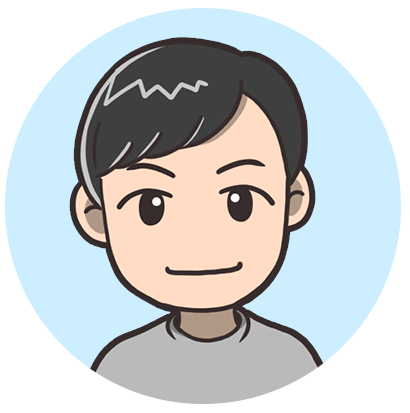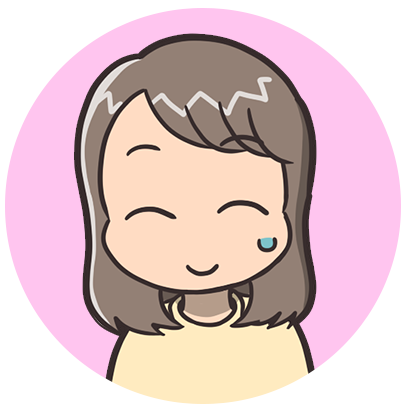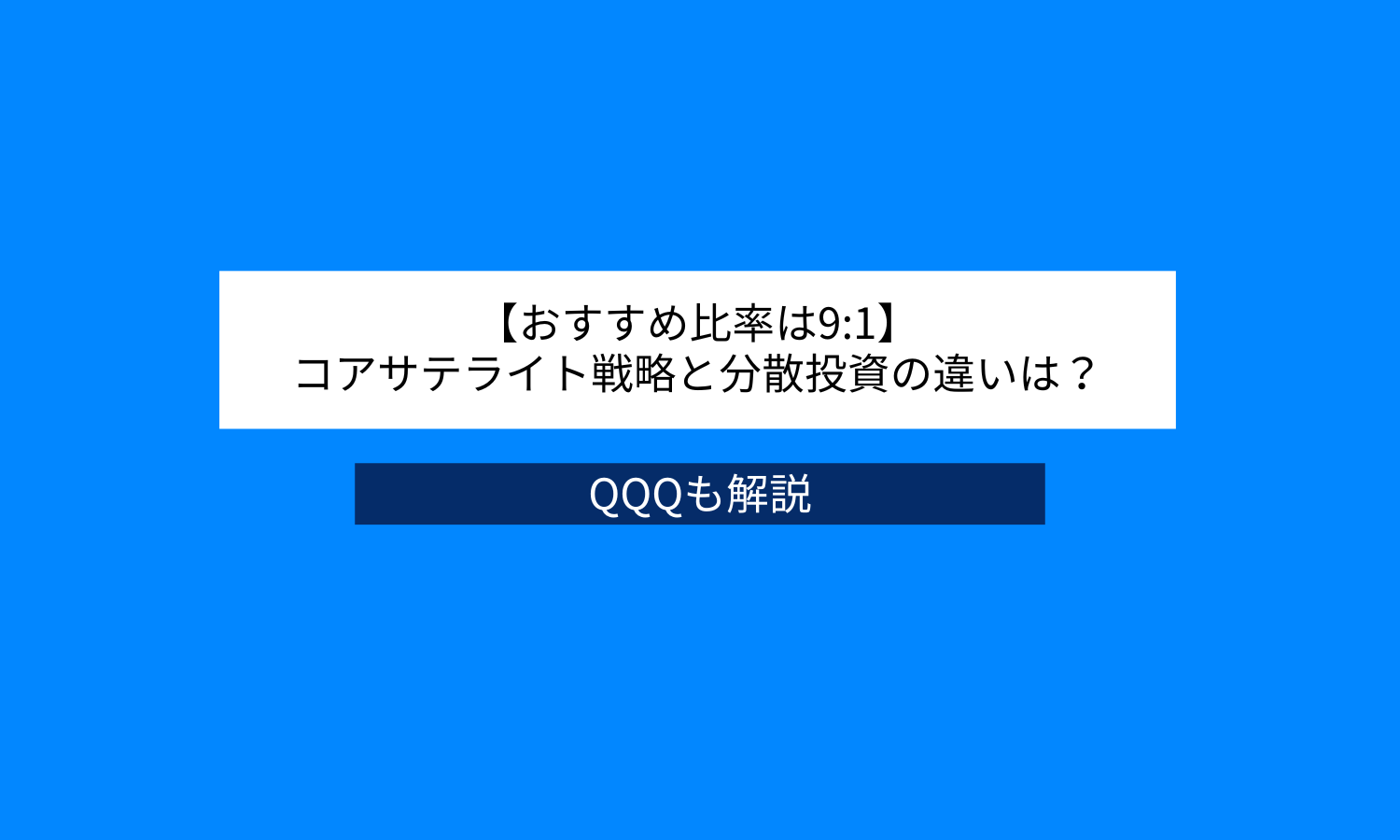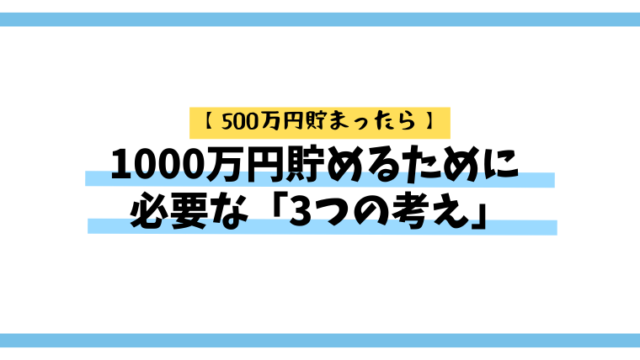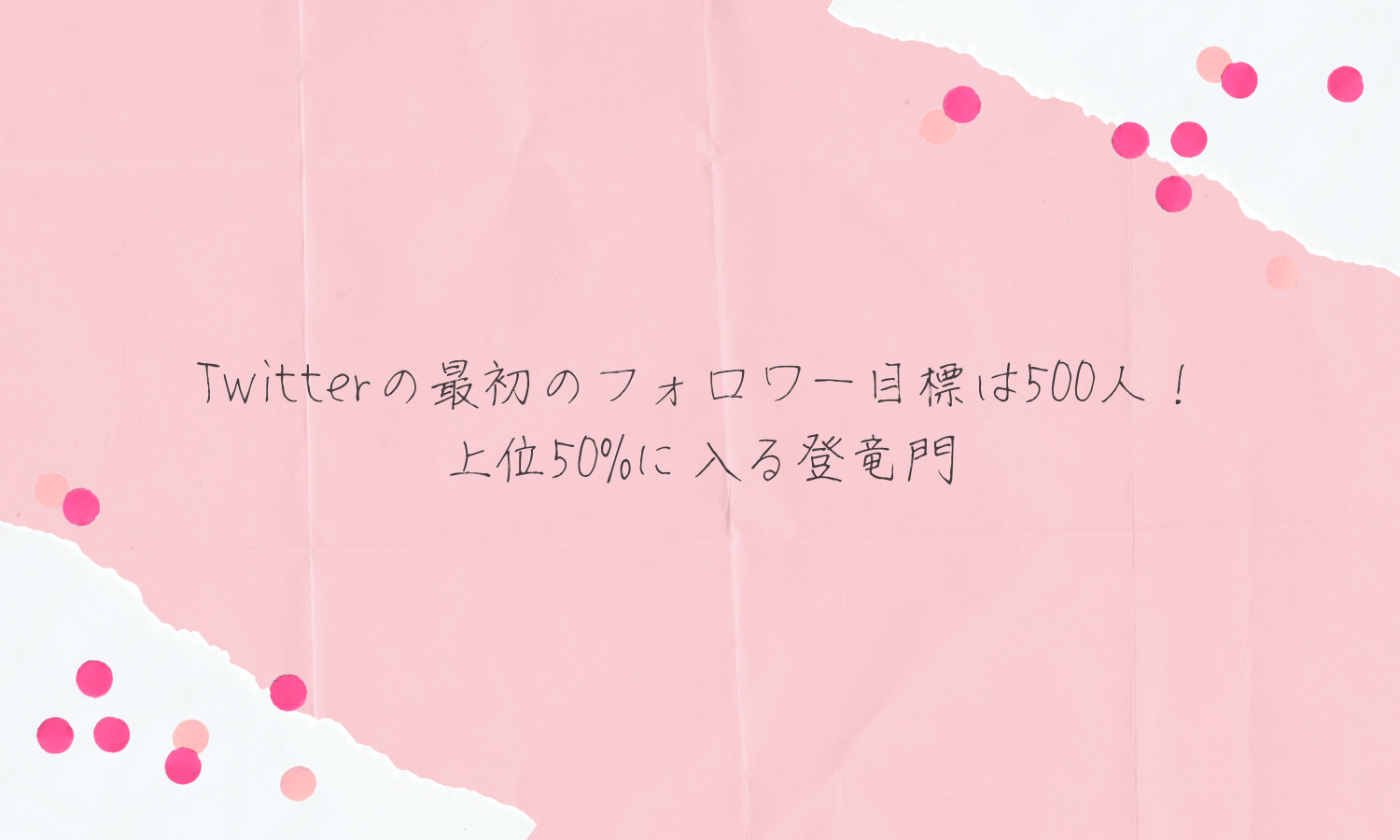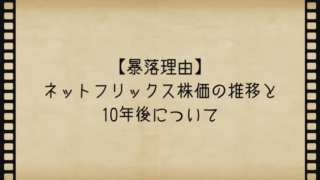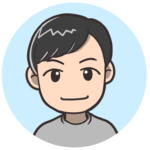パパ、一時期すごい流行った「レバナス系商品」って実際どうなの?
悪い商品ではないんだけど、レバナスは玄人向けなんだよね。
初心者が2倍儲かるからという理由で手出しするのは危険なんだよ。
パパもレバナスは一時期検討していたけど、結局通常のNASDAQへの投資に落ち着いたんだよね。
「楽天レバナス」は少しだけ手出した時期があるけど、結局は全部売却して手仕舞いしたよ。
手数料も高いし。
それでは、パパがレバナスをやめた理由も含めて教えてください♪
こんにちは!信託報酬0.2%以下を投資対象と決めているあいろん(@iron_money)です。
今回は、「楽天レバナス」についてやめとけと巷で言われている理由を考察していきます。
この記事は、こんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
レバナスの種類
パパ、そもそもレバナスという商品はどんなものなの?
種類はあるの?
レバナスは「NASDAQ100指数に対して投資成績が2倍になることを目指す投資信託」のことだよ。
ただでさえ値動きが激しいNASDAQにレバレッジをかけているんだから、初心者向けではなさそうだね。
レバナス系の商品は、下記の通りです。
| 商品名 | 運用会社 | 純資産 | 信託報酬率 | 設定月 |
|---|---|---|---|---|
| ①ifreeレバレッジNASDAQ100 | 大和アセットマネジメント | 2235億円 | 0.99%(税込) | 2018年10月 |
| ②楽天レバレッジNASDAQ100 | 楽天投資顧問 | 428億円 | 0.77%(税込) | 2021年11月 |
| ③auAMレバレッジNASDAQ100 | auアセットマネジメント | 223億円 | 0.4334%(税込) | 2022年7月 |
上記でわかるように、基本的には後に設定する商品の方が「信託報酬率」が引き下がっています。
基本的な考え方は、信託報酬率が低い商品に投資することで間違いありません。
わたしも今だったらauレバナスに投資するでしょう。
ただし、純資産額は後設定商品の方が低いので注意が必要です!
信託報酬率が低いからと言って、純資産額の兼ね合いもあるから皆すぐに他の商品に乗り換えるとは限らないんだね。
楽天レバナスの優位性
楽天レバナスは、楽天証券のみで取り扱っている商品になります。
楽天証券のランキング推移は下記の通りです。
| 買付ランキング | 積立設定件数ランキング | 値上がり率ランキング | |
|---|---|---|---|
| 2021年12月6日 | 6位 | 4位 | 32位 |
| 2022年4月26日 | 12位 | 14位 | 2638位 |
| 2024年4月24日 | 88位 | 76位 | 29位 |
設定時は株高だったけど2022年が株価低調だったから、そこでだいぶ風向きが変わったよね。
楽天レバナスの運用方針は、下記の通りです。
- 米国株式市場の値動きを享受する円建債券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする
- 日々の基準価額の値動きが「NASDAQ-100指数(米ドルベース)」の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指す
- 流動性等を考慮し、円建債券と米国の株価指数先物取引の配分比率を決定する
- 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う
※NASDAQ100指数とは…米国のNASDAQ上場銘柄より時価総額の大きい、金融を除く100社の株式で構成される株価指数
楽天レバナスの基本コンセプトは、「iFreeレバレッジNASDAQ100」と同様です。
現行のiFreeレバナスとの差は、「信託報酬」です。
発売当初はレバナス系最安となり、信託報酬が0.22%中々のインパクトでした。
今となってはauレバナス誕生で影が薄くなった感が否めません。
純資産額、信託報酬率とも中間を取っているのであえて投資する優位性は薄くなってしまいました。
楽天レバナスの危険性
楽天レバナスに限りませんが、レバナス系商品は「リスク」も多分に備えています。
NASDAQ100は1日で2-3%動く時もあるので、レバレッジをかけると5-6%の変動もザラです。
一日でそんなに価格が動いたら、安心して寝れなさそう…
基準価額変動が持つリスクについては投資信託説明書(交付目論見書)の4ページより確認ください。
上記の中で特筆すべきは「株価がもみ合った」場合です。
株価が上下を繰り返して元の100に戻っても、レバナスの場合は96までしか戻っていません。
レバレッジをかけていなければ±0だったものが、レバナスでは4%のマイナスになるのです。
上記は十分にレバナスの特徴として理解すべきです。
レバナスは初心者にはおすすめできないのは、この値動きの激しさだったのね…
リスク許容度をしっかり把握すべし
前述のリスクの高さ故、「レバナスはダメな商品か」と議論になることが多いです。
しかし、レバナスは使い方を間違えなければ非常に面白い商品だと思っています。
相場の上昇局面を予測し、少額のサテライト資産として持つ分には投資妙味を十分に味わえると考えます。
ただし、設定当初から70~80%の下落も覚悟しなければいけない商品だということもまた事実です。
下記を肝に命じましょう。
コア資産に向かない理由3選
- 変動額
- 投資スパン
- 手数料
前述の通り、レバナスは面白い商品には間違いありません。
しかし再三になりますが、取り扱い注意である事もまた事実です。
2018年、大和アセットマネジメントがiFree NASDAQ発売時に「ツミレバ」という概念を合わせて発表し、PRしました。
要旨としては下記になります。
上記のツミレバは一見魅力的に見えますが、一定期間を切り取って都合の良いように数字を見せている「再現性に乏しい」数字です。
コア資産には向かない理由を考えていきます。
①変動額
直近のコロナショック時、NASDAQ指数は1ヶ月で4割弱下落しました。
このタイミングで毎月資産の大半をレバナスに投資していたら…
とても常人ではまともな精神状態ではいられないでしょう(笑)
②投資スパン
そもそも「NASDAQ100」自体が元々短期~長くても中期向けの「キャピタルゲイン」向けサテライト運用が適切だとあいろんは考えます。
サテライト運用の考え方は、投資家ブロガーのたぱぞう氏がわかりやすいそうだよ。
参考にしてみてね♪
③手数料
わたしの個人的感覚としては、コア資産として長期で持つことを検討したら、楽天レバナスの0.77%の信託報酬は重いです。
パパ的にはiFreeレバナスの0.99%などは検討にも値しないらしいです。
経費率が0.1%以下の優良商品が多数ある中でレバナスの旨味を感じないってことだよね。
上記を肝に命じましょう。
- 2021年11月17日(設定時)・・・基準価額10,000円
- 2022年3月15日・・・基準価額6,181円
- 2022年3月30日・・・基準価額8,420円
- 2022年4月25日・・・基準価額6,408円
- 2024年4月24日・・・基準価額7,733円
※2024年5月追記
上記を見ても、例えばコロナショック時のような暴落時に1〜2年スパンで積み立てて上昇の利をとる、というのがレバナスの使い方だと感じます。
パパ自分で投資してみて、やはりコア資産や常時つみたてには向かない商品だと改めて感じたそうです(笑)
ラップアップ
今回は、「楽天レバナス」について考察していきました。
レバナスは「儲かる」と欲をかいて気づいたら資産が減っていた…となりがちです。
適切なリスクコントロールをしながら付き合っていきましょう!
最後に一言。
「ゆっくりと金持ちになることは簡単である」バフェット氏の言葉を胸に刻んで投資しましょう。
それではまた!