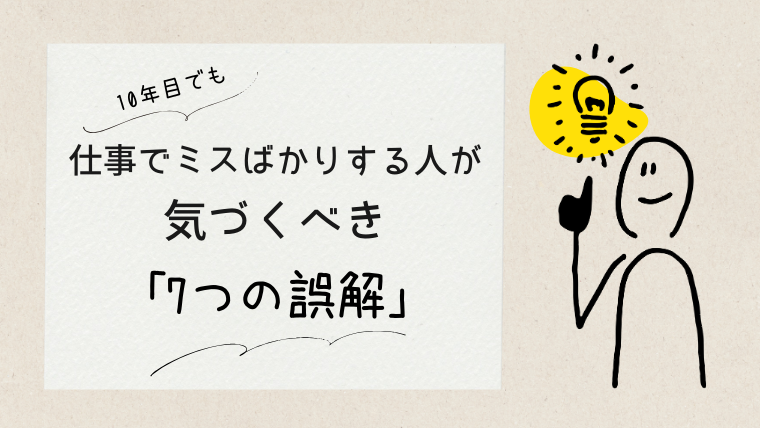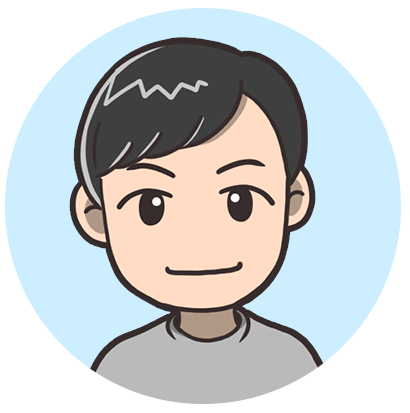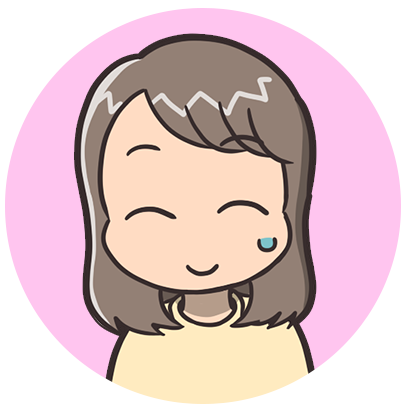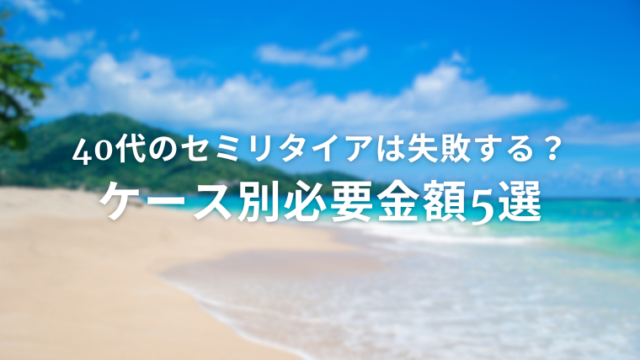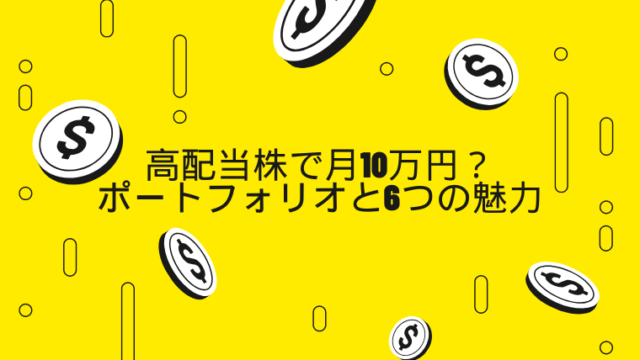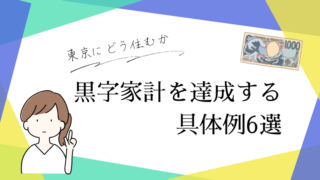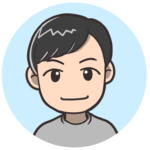パパ、ある程度仕事に慣れてきてもミスばかりで嫌になっちゃう時ってあるよね。
そるとちゃん、急にOLみたいなこと言うね(笑)
そんなときには、ぴったりの本があるよ。
「社会人10年目の壁を乗り越える仕事のコツ」この本を読むと7つの誤解に気づけるんだよ。
え、仕事を出来ないと思っている人には7つも誤解があるってこと?
是非詳しく教えてください!
こんにちは!いつからか、若手とは呼ばれなくなって立派なおじさんの仲間入りをしたあいろん(@iron_money)です。
今回は同世代の30〜40代「中堅社員」「ナイスミドル」に7つのメッセージを紹介します。
この記事はこんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
今回の参考書籍:社会人10年目の壁を乗り越える仕事のコツ

パパ、今回の参考書籍はどんな本なの?
「99%の人がしていないたった1%の仕事のコツ」などの99%シリーズはベストセラーにもなったので知っている人もいるんじゃないかな。
そんな99%シリーズで有名な著者、河野氏がピンポイントで「10年目」の社員を題材に狙い撃ちにしてきたのが本書です。
これは30〜40代のサラリーマンにとっては興味をそそられる内容です。
本書では「キャリア思春期」と形容していますが、30代半ばの10年目社員にはたくさんの悩みがあります。
わたし自身も思い返してみれば、新入社員時代の10年目の先輩と言えば「雲の上の存在」だったと記憶しています。
たしかに、ものすごい仕事の出来る大人に見えたよね(笑)
あの時の先輩と比べて今の自分は劣っているのではないか?なんて悩んだ日々もあります。
また、「10年目」と言っても置かれた環境によって全く状況は異なります。
ベンチャー企業や少人数の会社であれば経営者や責任者になっているパターンもあるでしょう。
年功序列の大企業であれば管理職どころか役職が何もない、なんていうパターンもあるでしょう。
著者の河野氏の強みは「幅広いキャリアを自身で経験してきたこと」なので書籍の内容に説得力があります。
そんな中から特にパパが「仕事でミスが多い人がしがちな誤解」について7つ解説していくよ♪
仕事が出来ない人の誤解7選
- 10年働いて「誇れる仕事」など1つあれば十分
- コンフォートゾーンの把握が重要
- キャリアの駆け出しでの出世はアテにならない
- 日系伝統企業の1社勤めは危険水域
- ブランドにこだわっても意味がない
- 昇進より空いた時間を有効活用する
- 「これから求められるスキル」は杞憂
10年働いて「誇れる仕事」など1つあれば十分
書店でチラッと立ち読みした際に上記の言葉が刺さり、購入しました。
「自己紹介の時にアピールできることは?」
「自分の強みはなんなのか?」
「今の環境以外でも自分は活躍できるのか?」
社会人10年目の人は常日頃、こんなことを考えています。
10年も働いて、何も誇れることがないと自己嫌悪に陥りがちです。
人生を振り返った時に、10年目なんて長い仕事人生の中でまだまだひよっこです。
パパも「30大中盤にもなって、仕事で誇れることなんて1つ2つしかないけどそれでいいんだと開き直れた」と言っています。
そもそも自暴自棄になっちゃったり自信をなくしちゃう方がよっぽど危ないもんね。
これは絶対みんな知っておいた方が良い考え方だよね。
コンフォートゾーンにいるかの把握が重要
仕事に慣れて余裕が出て、周囲からの評価も上がり、頼りにされ、充実感を感じる。これがとても良い状態なのは間違いありません。
上記はわたし自身も仕事の中で経験した感覚で、大変楽しく働けている状態だと思います。
問題は、コンフォートゾーンが長くなると「思考しなくても業務が捌けてしまう」ようになることです。
パパは「思考しなくても仕事がなんとかなってしまう状態」をコンフォートゾーンだと捉えています。
コンフォートゾーンにいすぎると成長機会が失われちゃうんだよね。
コンフォートゾーンの打破には千利休が茶道の世界で提唱したとされる「守・破・離」が効果的です。
「守・破・離」の考え方は仕事全体にも通ずる点があるよね。
まずは教えを守って、今より良い破り方があるか考え、最後に自己流にアレンジして離れる♪
1年単位で守・破・離を行い3年程度で仕事を考えたらどうかと本書は提案をしています。
3年以上同じ内容の仕事をしていて成長が実感できない場合、そろそろ一歩踏み出してみて「離れる」チャンスかもしれません。
キャリアの駆け出しでの出世はアテにならない
10年目くらいになると、周囲と役職やキャリアの差が出始めるタイミングです。
気になることも多いでしょう。
ただ、パパ的には「キャリアの駆け出しの出世」なんて全く関係ないと言っているんだよ。
サラリーマンあるあるとして「同期で最速で課長になる人と部長になる人は違うことが多い」という点が挙げられます。
多くの企業では30代半ば〜40代にかけて管理職の登竜門、課長になるタイミングで周囲との比較を余儀なくされることがあります。
しかしながら、そこから先のキャリアは全く別物です。
部長に登用される人は、多くの場合2〜3部門で課長で経験し、なおかつ在籍している課が好調であれば出世しやすくなります。
自分の力だけでチームを率いるわけではありません。
上司や部下、チームとしての総合力に左右されてその後のキャリアは決まっていきます。
特に他部署の人間の出世などは自分と比較してもしょうがないので、心を乱されるだけ損だとパパは思っているよ。
日系伝統企業の1社勤めは危険水域

下記のようなモヤモヤを抱えながら、社会人10年目で大きく悩んでいるケースは多いでしょう。
私もこの時期は特にバリバリ悩んでいました(笑)
一方で、下記のような不安もあります。
本書は、ズバリこの悩みに対して答えてくれています。下記に該当する場合は「転職活動」をするべきと断言しています。
- 社会人10年目前後
- 1社目の会社に所属
- 日本に本社がある日系企業
- 20世紀から続くような伝統的企業
上記の提言は、組織として硬直している可能性の高い会社に居続けることによって自分の市場価値が失われてしまう可能性のリスクを説いています。
外に出てみて変化への順応性を身につけた方が良いということなんだね。
パパは実際に上記に当てはまる会社から10年目で転職した人だもんね。
書籍の体現者だよね。
実際に行動した当事者からすると、上記は、間違いありません。
自分の市場価値や可能性の把握のためにも、転職活動は絶対に行うべきです。
10年勤めた会社でそれなりにやって来れた方は、転職先でもやっていける可能性が高いです。
今の評価と転職先の評価が大幅にズレるということは、可能性として低いことを知っておきましょう。
ブランドにこだわっても意味がない
上記のように、なんとなく守りに入っている方も多いと思いますがその考え方は無駄です。
本書はハッキリと、そのブランドが未来を保証しないことについて言及しています。
確かに言われてみればそうです。
わたしが就職活動をしていた時、航空業界や旅行業界といえば人気絶頂でした。
10年経過した今、転職で面接なしで入社出来ますと言われたらどうでしょう?
わたしは入社しません。
なぜなら「状況が変化した」からです。
ブランドなんて時が経てば変わるし、何の意味もないので過信NGということだね。
昇進より空いた時間を有効活用する
これは全ての勤め人にとって大きな問題です。
本書では下記のように説いています。
上記の考え方はわたしの根本になっています。
「他責思考」にとらわれて会社を悪者にしても何も始まらないので、出来ることを自分ではじめるという考え方だね♪
わたしも会社を辞めてみてから実際に「クラウドワークス」や「ランサーズ」を活用して、お金を稼ぐのには色々な手段があると実感しました。
「これから求められるスキル」は杞憂
本書ではわたしも抱えていた上記の悩みに対して、「杞憂」だからそんな事考えなくて良いとバッサリ回答してくれています。
「変化に柔軟である事」これだけが激動の時代を生き抜く唯一のスキルなんだよね♪
わたし自身、これからの時代に「ITスキルは必須」と考えIT業界に転職しました。
しかし体感してみて1番重要だと感じたのは、スキルよりもマインドセットでした。
以前の職場では、従前踏襲型の仕事の進め方が良しとされていました。
それが今の職場では通用しません。
日進月歩のIT業界で、「前はこうやっていた」とか「以前のやり方を踏襲しよう」なんていう人間は生きていけないそうです。
パパも最初はかなり戸惑っていました。
わたしの場合はIT業界への転職によって、結果的に変化に対する意識を研ぎ澄まされたイメージです。
これは間違いなく自分のスキルとして計上できると自覚しています。
ラップアップ
今回は同世代の30〜40代「中堅社員」「ナイスミドル」に7つのメッセージを紹介しました。
サラリーマンはいくらでも自信をなくせる一方で、自分の能力や可能性を過小評価しがちです。
自分に自信が持てないとき、今回の参考書籍は読んでみると良い一冊だと言えるでしょう。
最後に一言。
サラリーマンを10年も続けられたこと、それは実はすごい希少価値です。自信持っていきましょう!
それではまた!