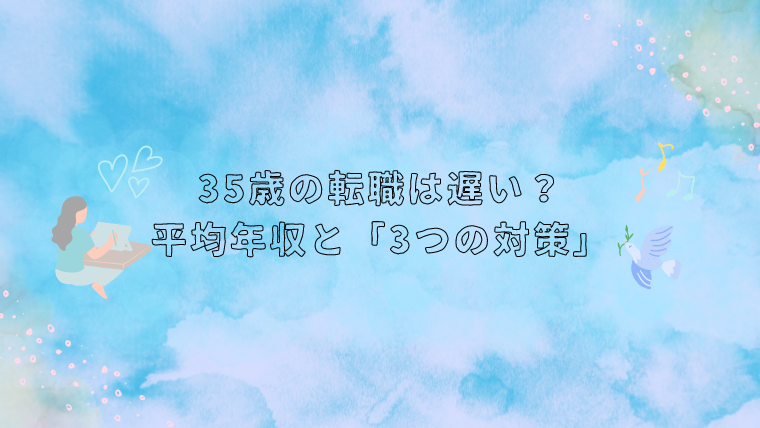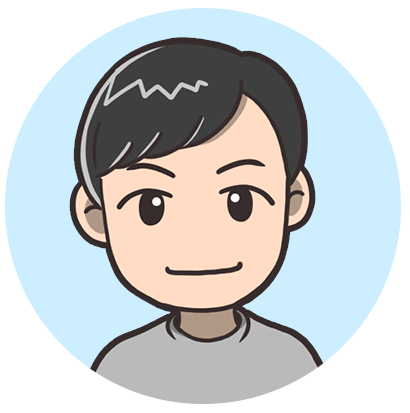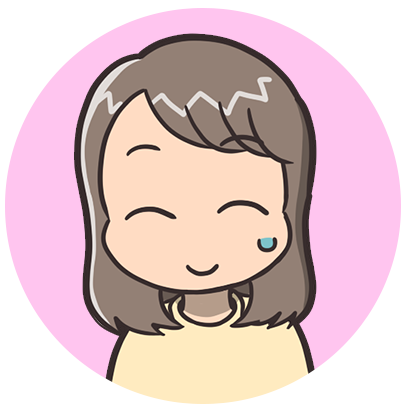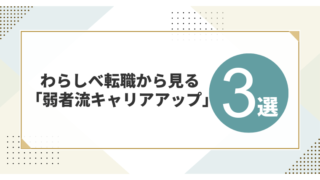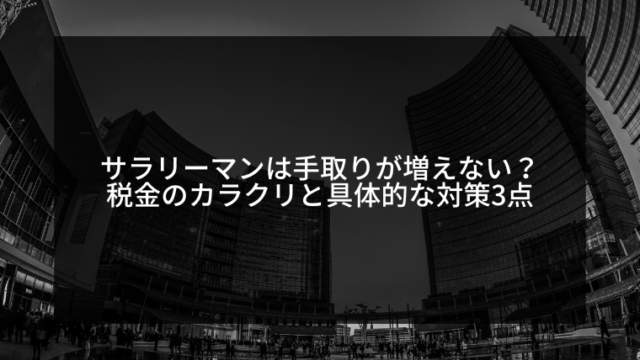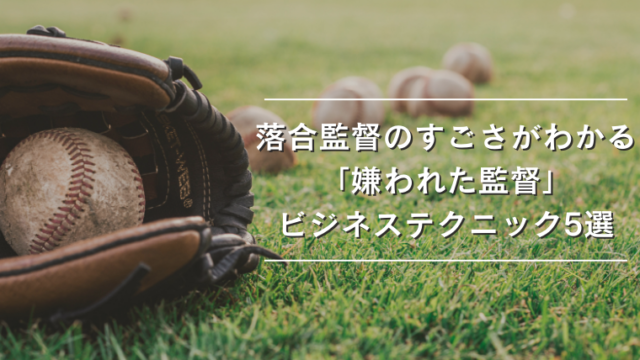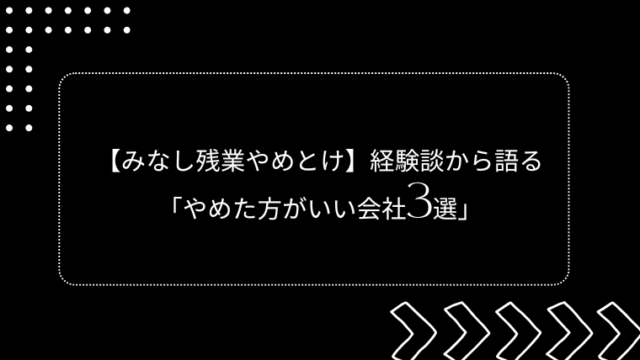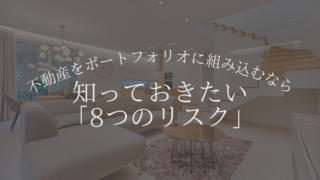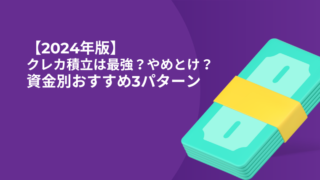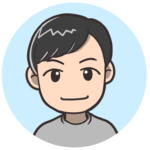パパは30代で転職したとき、なんか苦労したことある?
具体的に考えてから、数ヶ月くらいで決まっちゃったよ。
「30代は転職手遅れ」とか「35歳転職限界説」とか昔の話だと思うよ。
逆に転職がうまくいってない人は、絶対理由があるからね。
パパは転職前から情報はずっと集めてたもんね。
たまにエージェントさんと話したりして。
なるほど、転職にはコツがありそうだね。
その辺、詳しく教えてください〜♪
こんにちは!30代で転職を経験したあいろん(@iron_money)です。
今回は、「転職とキャリアアップ」をテーマに記事を書いていきます。
この記事はこんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
30代の平均年収について
パパ、そもそも30代の平均年収ってどれくらいなの?
そうだね、まずは平均から見ていこう。
株式会社ジョイントが運営する転職情報メディア「Carrer Theory」に興味深い記事が掲載されています。
本記事では「民間給与実態統計調査」より引用されている通り、平均年収は下記になります。
- 30代前半 413万円
- 30代後半 449万円
男女比もあり、例えば30代後半の男性に限定すれば年収は「533万円」まで上昇します。
ふむふむ、それでは「30代後半」で「年収600万円」貰えるようになれば平均より上と言えそうだね。
30-40代は心技体全てが揃っている状態で、どの企業でも中核をなします。
商品として「脂が乗っている」状態です。
業界や職種選びを丁寧に行えば、年収もアップしやすい状態になっています。
パパも転職せずに最初の会社に居続けていたら、「今と年収ベースで300万円くらいは違うのでは」と言っていたよ。
20代は横一線だから差が出にくいけど、30代以降は業界や規模が給与に直結しがちなんだね。
参考書籍「転職の思考法」
「30代は転職するには手遅れ」
「35歳を過ぎたら同業種以外への転職は不可能」
男女比もあり、例えば30代後半の男性に限定すれば年収は「533万円」まで上昇します。
年齢にして30〜40代は「社会」「仕事」について理解が深まり、「ライフステージ」の基礎が固まってくる年代です。
転職の有無はさておき、自分の市場価値を明確にしておくと有事の際に自分を助けてくれます。
転職に関する情報は入れておくとベターでしょう。
個人的に「転職の思考法」は非常に明快かつ再現性が高かったです。
今回は「転職の思考法」をベースに「転職がうまくいかない人の共通点」について3点解説します。
転職がうまくいかない理由3選
- 「転職する」と「転職できる」を混同する
- 「会社選びの3つの基準」を理解してない
- 「やりたい事」を仕事にしたがる
「転職する」と「転職できる」を混同する
わたしが書籍「転職の思考法」内で1番腹落ちしたのは、下記の言葉です。
大事なのは転職よりも「転職できる」というカードである
「転職」をうまく捉えられずに失敗する人は、総じて下記のような状態が多く見受けられます。
- 転職活動=必ず転職しなければならないと思っている
- 現在の会社が嫌で仕方ない
- 転職を前提として転職活動する
- 自分の市場価値を図ることを長年怠っていた
- 急に環境や状況が変わって転職活動をはじめた
上記は考え方が極端なので、転職活動の妨げになります。
もっと転職についてゆるく考えるべきなんだね♪
パパが、本書で気に入っている言葉を紹介します。
「いつでも転職できるような人間がそれでも転職しない会社。それが最強だ」
「転職する」は結果論です。
今は必要ないかもしれないし、ベストではないかもしれません。
ただし、「転職できる」は誰でも必ず用意しておく必要があります。
「転職できるけど自ら留まる選択をしている」という考え方が仕事や人生においてもたらす恩恵は計り知れません。
パパも「転職できる」状態で2年くらい働き続けてから、大手企業の募集がかかったタイミングでチャンスを掴んで転職した経緯があるんだよ。
企業には「急に募集がかかるタイミングがある」というわらしべ転職の考え方をパパは採用しています。
「会社選びの3つの基準」を理解してない
本書には3つの「会社選びの基準」が登場します。
転職がうまくいかない人は「転職したい」という気持ちだけで基準が曖昧な人が多いです。
下記の3基準を整理しておきましょう。
- マーケットバリュー
- はたらきやすさ
- 活躍の可能性
マーケットバリュー
その会社で働くことによって、自分の市場価値は高まるのか?という観点。
それが「マーケットバリュー」です。
パパは転職を決めた理由として「新卒から1つの業界に居続ける危機感」があったそうだよ。
最初に従事した業界が斜陽産業だと、その傾向はより顕著になります。
「その会社でしか働けない人」になっちゃうんです。
マーケットバリューを活かすという観点では「わらしべ転職」という手法が参考になります。
興味があれば書籍を手に取ってみると良いでしょう。
「社内で仕事できる人」と「市場価値が高い人」はイコールではないという真実に気付かされるよね。
たしかに採用側も「1社で成功した経験」と「3社で違う環境に適応した経験」だったら後者を取りたくなるかも。
はたらきやすさ
その会社が「自分にとって」はたらきやすいのかどうか。
これはめちゃくちゃ重要なテーマです。
例として、あいろんのケースを挙げてみます。
わたしは下記のような、自覚している特性があります。
上記より、気質が大企業ではなく「ベンチャー向き」と言われることがありました。
しかしながら、30代に差しかかると下記のような気持ちも生まれます。
上記には「時間の確保」が必要不可欠です。
20代で仕事に莫大な時間を費やしたので、30代以降はバランスを取っていきたい思いが強くありました。
結論として、パパは「大企業の新規事業やDX化の立ち上げフェーズ」という環境に身を置くことを決めました。
結果的にはわたしの「わかりやすい成果を求める」という考え方は大企業の新規事業の領域とマッチしたので良かったです。
上記のように個人の性格や環境にも左右されます。
他人が決めた「優良企業」など何の意味もないってことだね。
自分が働きやすいかどうかが重要だね。
活躍の可能性
本書では「活躍の可能性」も大切な要素だと言及しています。
特に会社によって全く異なるのが「部署のパワーバランス」です。
同じ営業職だとしても、営業の裁量や発言権が大きい会社から小さい会社に転職した場合にはやりずらさを感じるケースが大半でしょう。
「やりたい事」を仕事にしたがる
本書によると、人には2種類のタイプがあり「to do型」と「being型」があり、下記のように分かれるそうです。
「世の中に革命を起こす」「会社を立ち上げて大きくする」などto do型の仕事は非常にわかりやすいので、魅力的に映ります。
一方でbeing型は「尊敬できる人とはたらく」「周囲に喜んでもらう」などto do型に比べると少し平凡に見えがちです。
本書には衝撃的な記載として、「99%はbeing型の人間である」と説いています。
実はわたしも上記で悩んだことのある人間の1人です。
特に仲の良い「to do型」の友人と語るときにどうしても自分がちっぽけな存在に思えた経験があります。
「わかる!」と思ったあなたは、ぜひ手に取って読んでみてください。
きっと新しい考え方の発見があります。
パパは20代のとき良く仕事で悩んでいたけど、「自分はbeing型だから」と割り切った後の方がなんだか楽しそうに見えます。
キャリアアップ転職のメリット
- メリット①会社依存マインドがなくなる
- メリット②汎用性のある自己スキルがわかる
- メリット③変化に対して柔軟になる
- 番外編:過度な期待は禁物である
ここからは具体的な「キャリアアップ転職」のメリットについて3点紹介します。
メリット①会社依存マインドがなくなる
会社依存マインドは、新卒で入社した会社を退職する際に必ず断ち切らないといけない思考です。
新卒で入社した会社を辞める事には、少なからず抵抗があるパターンが多いでしょう。
順調に勤めていれば、下記の様な資産が積み上がっている可能性も高いです。
「社内知識」
「各セクションキーマンの把握」
「過去の経緯」
上記などが頭に入っている状態なので、その会社においてはパフォーマンスを発揮しやすい環境になっています。
わたし自身も退職時に、周囲から言われた言葉は上記に関連するワードが大半でした。
「せっかくやってきたのにもったいない」
「また1からやるの大変だよ」
「近々あいろんは昇格すると思うよ」
「今の評価が良いのに、成功する保障がないところになぜいくのか」
パパが転職してみて1番感じたのは「会社とは狭い世界だったんだな」ということだそうです。
辞める前はもったいないと思っていても、捨ててみたら新しいものが入ってきます。
組織も同様で、自分が抜けても結局は違う人間が同じ機能を担って回っていきます。
このように、「組織とはなんたるか」を身をもって体感できる事は転職の大きなメリットです。
何事も依存するのはリスクです。
会社に依存せず、自分自身の選択で働き方を選べると思えるだけで強い自信が生まれます。
特にパパは転職を経験してから、毎年の人事情報に一喜一憂している人たちを俯瞰して見れるようになったそうだよ。
人事で誰が上がろうが、極論はどうでもいいことです。
「自分で人生を選択している」というマインドが重要です。
メリット②汎用性のある自己スキルがわかる
前述の通り、仕事において業界の慣習や言葉は重要です。
但し、上記と「自分の強み」は別物です。
特に環境が変わる転職の際、強みが強制的にあぶり出されるというメリットがあります。
わたしの場合、前職で手段として活用していたもの(例えば特定のシステム利用方法や業界特有の知識)はその後の人生に役立っていません。
役立つのは下記のような汎用性のあるスキルです。
上記は普遍的なスキルであり、「人の心をつかんで動かす」スキルは特に汎用性のあるスキルだと転職してみて改めて認識しました。
メリット③変化に対して柔軟になる
人間は、一度も経験していないものに対して拒否反応を示す「現状維持バイアス」という特徴を持っています。
これは、逆にいうと一度経験しておくと非常に目線がフラットかつクールに保てると言う事です。
例えば、下記のような状況の時に動き出しが早くなります。
変化と向き合って対応できる「柔軟性」が備わっていれば、有事の際も自分で考えて行動することが出来る様になります。
言葉にするととてもシンプルに聞こえますが、変化への耐性を上げておくことは満足度の高い生活と相関性があります。
転職は半強制的に変化への耐性を強めてくれるメリットがあります。
番外編:過度な期待は禁物である
ここまで転職のメリットとして3点挙げましたが、大事なのは言うまでもなく「心構え」です。
自分の人生を自分で切り開くために行動し、既にある心地良いものを捨て、現状維持バイアスを打ち破り変化を許容した先に「転職のメリット」はあります。
従って、下記の様な場合は残念ながら転職してもメリットを得られにくい可能性があります。
「嫌なものから解放されたい」という動機の場合、転職しても同じような気持ちになる可能性が高いと言うことは心がけておきましょう。
ラップアップ
今回は、あいろん自体の経験も踏まえて「転職がうまくいかない理由」を記事にしました。
最後に一言。
これからの時代、一つの環境に長年留まる事こそ本当のリスクだと思っています。
それではまた!