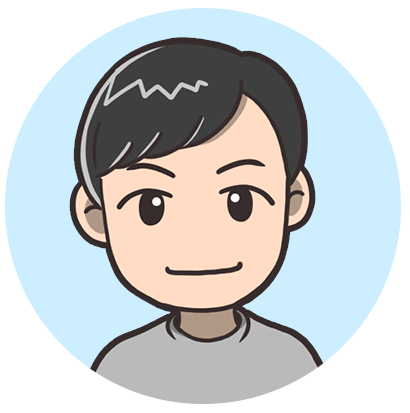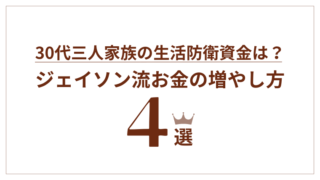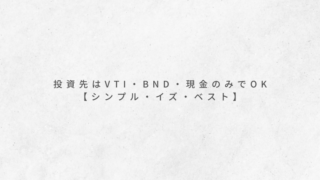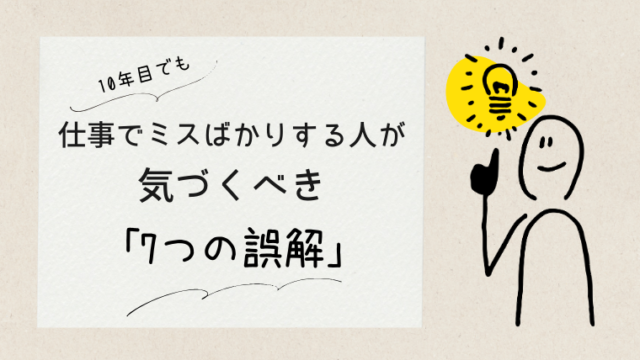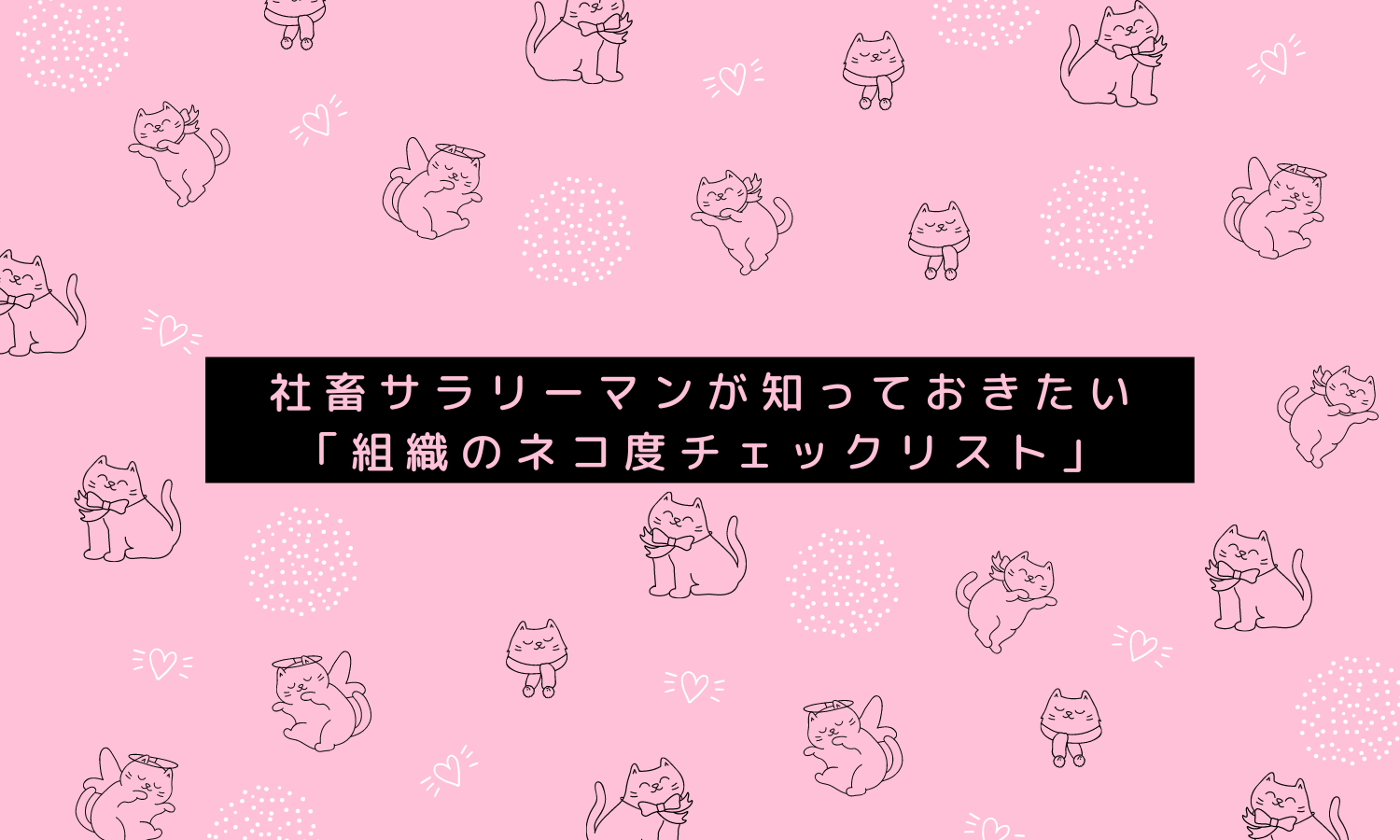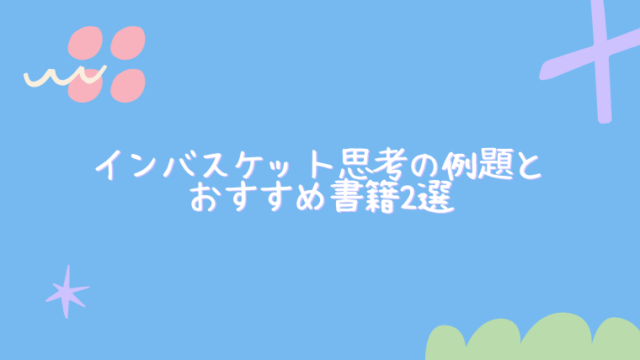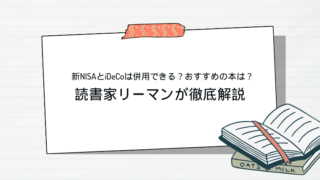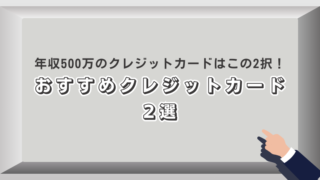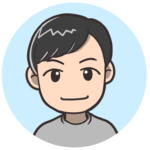ねぇねぇ、パパは投資信託とETFだったらどっち派?
そるとちゃん、中々切れ味鋭い質問だね(笑)
インデックスファンドの購入は投資信託をメインにしているけど、ETFにも良い部分はたくさんあるんだよねぇ。
パパは併用しているよ。
そうだよねぇ、経費率が低かったりとか売買の流動性が高いのはETFの大きなメリットだよね~。
(知ってて聞いてきたのか…恐ろしい子)
こんにちは!ETFの奥深さに魅了されはじめているあいろん(@iron_money)です。
今回はわかりそうで良くわからない「ETF」について関連書籍をベースに解説します。
パパ曰く、何十冊も読んだけど結局ETF説明書籍で群を抜いてわかりやすいのは「ETFはこの7本を買いなさい」だそうです。
この記事はこんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
「ETFはこの7本を買いなさい」がETF系の書籍でおすすめできる3つの理由
本記事にたどり着いてくれているあなたは、「ETFに興味がある」状態で何か参考になる情報を求めているでしょう。
わたしはETFの理解を深めたければ「ETFはこの7本を買いなさい」を読むことが最善だと考えています。
資産形成の一角としてETFを所有することはとても簡単です。
上記だけで、誰でも世界中の優良ETFが購入できます。
そんなETFの関連書籍は探せばたくさんありますが、個人投資家は書籍に下記の情報を求めています。
上記全ての要素を満たしてくれているのが朝倉氏(モーニングスター代表)の著書「ETFはこの7本を買いなさい」です。
2017年6月に初版が発行され長らく人気を博していた本書ですが、2022年2月より内容をリニューアルした「改訂新版」が発売されています。
初版発行以来、世界情勢は目まぐるしく変化しています。
著者が情報をアップデートしてまとめ直してくれているので、前回の書籍を読んでいても再度買い直して読みたくなる内容です。
金融商品の括りでは比較的あたらしい「ETF」は、現在でこそ優良性が認知され関連書籍は毎月のように発刊されています。
パパ的には、ETF紹介系の書籍は本書を薄めたような内容が多いと感じているそうだよ。
本書ではETFの特徴を下記のように述べています。
- コストが安い
- 柔軟に売買できる
- 品揃えが豊富
- 特色のあるものが多い
また、本書を読むに従って下記の流れが自然とわかります。
「どの銘柄が自分にとって投資対象となるETFなのか?」思考整理しながら読み進められる内容になっています。
インデックスファンドの意義
本書では具体的なETFの説明の前に、下記がわかりやすく学べる構成になっています。
1976年、バンガードグループより世界初の個人向けインデックスファンドが発売されました。
インデックスファンド発売当初は「臆病者の投資」として嘲笑されていたのも今は昔。
現代でインデックスファンドは投資において最適解の地位を築いています。
インデックスファンドへの資産流入の勢いは目覚ましく、2010年時点で米国で19%しかなかったシェアが2020年には40%にまで上昇をしています。
2017年の初版発行時に本書で予見していたトレンドは、より大きくうねりを上げていることが見て取れます。
アクティブトレーダーの象徴であるウォーレン・バフェットさんが「死後は資産の9割を米国系のインデックスファンドに投資するよう妻に伝えている」逸話も有名だよね。
インデックスファンドを大幅に上回る「年平均22~23%」リターンを叩き出す稀有な投資家のバフェット氏でさえ、資産構築にあける再現性においてはインデックスファンドを何よりも信頼している証拠です。
アクティブファンドとインデックスファンドの違い
アクティブとインデックスの違いとして大別すると、下記になります。
- 市場平均並みの投資収益を目指す
- 国内株式系商品の信託報酬平均0.57%
- 市場平均以上の投資収益を目指す
- 国内株式系商品の信託報酬平均1.56%
- 過去10年間で、7~8割のアクティブファンドはインデックスファンドに負けているデータがある
アクティブファンドは旬なテーマを取り上げます。
優秀なファンドマネージャーがあの手この手で収益をあげる手段を考え、実行します。
それでも7〜8割は市場平均「並み」を目指すインデックスファンドに負けるのはなぜでしょう?
手数料の1%差は致命的である
投信には「販売手数料」と「信託報酬」の主なコストがありますが、手数料1%の差は致命的です。
例をあげてみます。
- 信託報酬0.5%…2,427万円
- 信託報酬1.5%…1,811万円
616万円の差で、利回りとしては34%の差がつきます。
1%の手数料差でここまでの大きな話になるなんて!!
本書には「手数料差が理解出来ないとETFの本質的なすごさが理解できないよね」という著者の気概を感じるほど、丁寧な解説が光ります(笑)
投資における最適解として有識者は概ね「インデックスファンド」をすすめますが、それなりに理由があるということです。
海外ETFについて
アクティブとインデックスの基本を抑えたところで、ETFの説明に入っていきます。
ETF(Exchange Traded Fund)日本語で「上場投資信託」と呼ばれます。
ETFと投資信託の違いについての一般論は、下記の通りです。
- 上場している投資信託である
- インデックスファンドが大半
- 株式同様、取引時間ならいつでも売買できる
- 販売会社が存在せず、信託報酬が低い
- 株式ETFだけでなく、多種多様な種類がある
- 分配金再投資は自分で行う必要あり
- 単なる投資信託という時は、非上場を指すことが一般的
- 投資信託は約6,000本
- 投資信託の値段は1日に1回決まる
- ETFに比べると信託報酬が割高なことが多い
- 分配金の再投資ができるので複利を活かしやすい
運用スタイル
上記のような特徴を鑑み、本書でも下記のような運用スタイルを取れると述べています。
サテライトETF手法に関しては、パパが過去記事でも取り上げています。
個別株に比べて初心者が取り組みやすいサテライトで経費率も低い優良商品が多く、おすすめです。
また、ETFは「まとまった投資」に向くため、小口投資の場合は非上場のインデックスファンドの方が優れているという意見にも説得力があります。
本書でも繰り返し述べられていますが、ETFの利点は「低水準な信託報酬」「株式のようにリアルタイム取引や指値もできる機動性」の2点に集約されます。
その中でも特に経費率が低く分散が効いている「海外ETF」に投資することを筆者はすすめています。
海外ETFはコスト競争が激しく、純資産残高が増えると信託報酬を引き下げることが多いです。
一例としてバンガード社の「VT」はETF一本で全世界株式をカバー出来ることで有名です。
このVTですが、以下のように信託報酬を引き下げています。
2024年現在は「0.07%」まで信託報酬が引き下がっています。
信託報酬は長期で見た時のリターンの差に大きく影響を与えるもんね。
この低水準はほんとありがたいよね。
ETFを取り巻く外部環境
第三章では「米国個人投資家がなぜこぞってETFを購入しているか」を取り上げています。
興味深いのは、下記のアンケート結果です。
- 低コスト(40%)
- セクターへの直接投資(30%)
- 日中取引(26%)
※米国人投資家ETF購入理由より抜粋
米国投資家に「なんでETFを選んだの?」と聞いたら「コストが安いからに決まってるじゃん」と返される可能性が4割あるということですね(笑)
ただ「セクターへの直接投資」と「日中取引できる」点が気に入られているのは押さえておきたい知識です。
そんなETFは、近年3社寡占状態が続いています。
- iシェアーズブランドの「ブラックロック」
- インデックスの生みの親、ジョン・ジャック・ボーグル率いる「バンガード」
- スパイダーブランドが有名な「ステイト・ストリート」
ETFはこの上位3社だけで8割を占めています。
ETFを購入する際に必ず関わる3社なので存在だけでもしっかり覚えておくと良いでしょう。
またETFの特徴として下記があげられます。
- 特定業種や地域への投資を容易に行えること
- 取引に柔軟性があること
特に運用に少し慣れてきた人がポートフォリオの微修正をかけたい時には非常に有効な手段となり得ます。
セクター別ETFの使い方一例(AmazonやTeslaへの投資を使いたい場合)
セクター別ETFの使い道として一例を紹介します。
一般消費財セクター集中型のETFであるバンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF(ティッカー:VCR)を見てみるよ。
個人投資家なら一般消費財セクターに分類されているAmazon(ティッカー:AMZN)やTesla(ティッカー:TSLA)への投資を検討した事がある方も多いでしょう。
パパも上記2銘柄に興味があるのですが、「Amazonは手を出しづらい」「Teslaは値動きが激しすぎて個別で買うのが怖い」とも考えていました。
そんな時に便利なのが「セクターETF」の中で一般消費財セクター304銘柄に投資しているVCRです。
VCRの構成割合TOP2であるAmazon、Teslaの構成割合は2024年現在、下記の通りです。
3位以降はホームデポ、マクドナルド、ナイキ、ロウズ、スターバックス…と続いていきます。
上記のようにセクター別ETFを使う事で、簡単に投資対象への比率を高められます。
これはサテライト的な使い方としてとてもおすすめできます。
ETF購入前のチェックポイント
「ETFはこの7本を買いなさい」ようやく第4章からは具体的なETFの購入に入っていきます。
とはいっても、まだまだ購入には至りません。第4章は購入前の確認や自分の目標を決めるフェーズです。
本書では、下記の通り投資家を目標利回り別に定義しています。
いずれにしてもETFを数本組み合わせれば10年利回りは6%程度になるデータが紹介されています。
パパ的にも違和感ないレベルのリスクリターンだそうです。
ただし、本書でも述べられている通り「長期的」目線での内容なので、短期でETFを使って利ザヤを取りたい手法とは全く異なります。
ETFはこの7本を買いなさい
ようやく第5章で辿り着くのが、本書のタイトルにもなっている「ETFはこの7本を買いなさい」です。
最初は「結論を引っ張りすぎだろ」と思いましたが(笑)よくよく何回も読み返すと、しっかり理解を深めてから具体的なETFを通じて「自分流のポートフォリオがカスタマイズできる」というETFの利点を伝えようとしてくれている、著者の意図を感じられます。
個人投資家にとって良いETFについては再三述べられていますが、下記が基準です。
詳細については本書に書いてありますが、厳選7本に入っている中でパパが実際に購入している3本を例に挙げて紹介するよ。
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
- ティッカー:VT
- 運用会社:バンガード
- 信託報酬:0.08%
世界全体の株式時価総額の98%以上を1本でカバーする「全世界株式型」ETF。
47カ国8,000銘柄に投資出来るので、投資に興味はないけど何か運用したいと言われたら「とりあえずVT」と言えるほど、完成されたETFです。
本書においても中心的に使用されるETFです。
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
- ティッカー:VTI
- 運用会社:バンガード
- 信託報酬:0.03%
2017年時点では厳選7本から漏れて後述する「その他の13本」扱いだったVTIですが、新版では「この7本を買いなさい」に格上げされました。
VTが全世界への投資なら、VTIは全米約4000銘柄へ投資できる「全米株式」として世界的にも非常に有名です。
VTIについてはパパが過去紹介している「ジェイソン流お金の増やし方」や「父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え」など数々の良書でも投資先のメインとして推奨がされています。
バンガード・米国トータル債券市場ETF
- ティッカー:BND
- 運用会社:バンガード
- 信託報酬:0.035%
「株式ほどリスクを引き受けたくない」
「手堅く利回りは取りたい」
上記時に投資候補筆頭に上がるのは「債券」ですが、中でも米国適格投資債券を対象としています。
7割以上をAAA格(優良債券)が占めているBNDが債券ETFの中でもトップクラスの優良商品として今回ランクインしています。
因みに2017年版での米国債券ETF枠はブラックロック社の「AGG」でしたが、今回の新版ではバンガード社の「BND」に変更がされています。
AGGもAAA格は7割以上を占めており約6,000銘柄への分散投資、信託報酬の低さも0.05%と申し分なしです。
しかしながらBNDの「約1万8000銘柄への分散投資」「信託報酬の0.35%」とそれぞれAGGを上回っている点から新版で変更されたと推測しています。
名著「父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え」においては投資先はVTI、BNDの2つのみで良いと断言されています。
まさに本書で紹介されている2つのETFを組み合わせるだけのポートフォリオを著者が最愛の娘にすすめているという点からも素晴らしいETFであることが伺えます。
本書内厳選7本ETFは「組み合わせることで低コストでポートフォリオを組むことができる」利点があります。
7本全て購入しなくても、「父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え」で紹介されたVTI+BNDの運用や、厚切りジェイソン氏の「VTI一択運用」のようにビビッときたものを数本買うだけでもかなりタメになるのでおすすめです。
本書内では結論だけでなく、かなり細かい「7本を組み合わせたシミュレーション」がポートフォリオ別に記載されています。
こだわりたい人に向けたETF13本
個人的には本書内で1番面白いのは第6章「もっとこだわりたい人へ一歩進んだETFの活用法」だと思っています。
これは投資をある程度やりこんでいる人ほど勉強になるとパパは言っていたよ。
前述のVTやBNDはコア資産として低コスト、分散が効いている優良商品であることに疑いの余地はありません。
しかしながら、厳選7本は「サテライト資産」向きかと言われると疑問が残る点もあるのは事実です。
そういう意味では、本書で取り上げられている13銘柄はサテライト向きのパンチが効いているものも含まれています。
また、新版ではだいぶ銘柄が入れ替わっており、一見の価値は十分あります。
13銘柄にランクインされている中で情報技術セクターETFの「VGT」やハイテク銘柄への投資比率が高い「QQQ」などはサテライト投資銘柄として非常に優秀で投資対象となり得るでしょう。
また、債券に関しては安全度が高いBNDに比べるとは安全度が低い代わりに配当利回りが高いステート・ストリート社の「JNK」などが含まれています。
上記のように本書は最初に明示される7銘柄で「原理原則や王道」を押さえつつ、その後の13銘柄から「自分なりのスパイスを加えてカスタマイズを図る」という構成になっています。
正直、この20銘柄の紹介を読むためだけでも十分面白い内容になっています。
新NISAへの対応検討
パパ、新NISAが2024年からはじまったけどETFを活用するのはアリなの?
結論的には全然ありだよ。
「成長投資枠」で年間240万円までETFを購入出来るから、下記のような場合には検討しても良いかもね。
ただ、「資産の最大化」を新NISAに求める場合には投資信託の方が効率が良い場合も多いので注意です。
パパが「新NISAの投資戦略」は記事にしているから参考にしてみてね♪
ラップアップ
今回はわかりそうで良くわからない「ETF」について関連書籍をベースに解説していきました。
本書紹介の20銘柄を中心に、自分なりのポートフォリオを組んでいきましょう!
最後に一言。
パパは魔法のようにETFのアルファベット3文字ぶつぶつ言っている時があります…
それではまた!