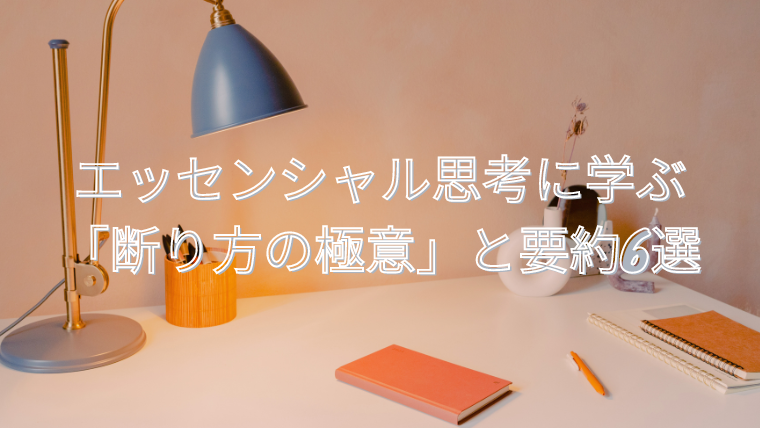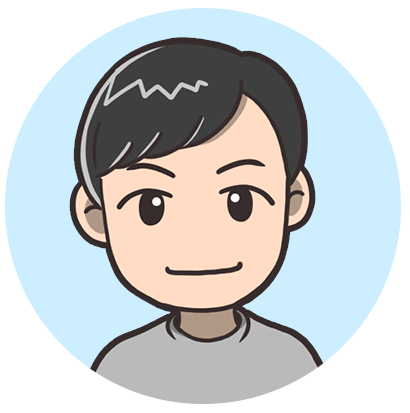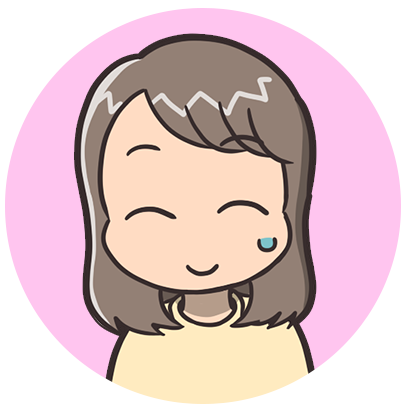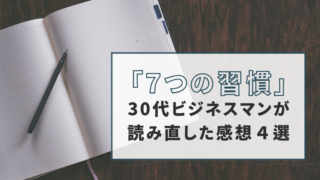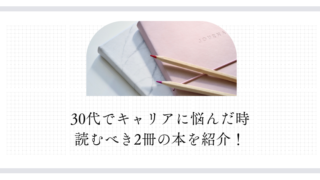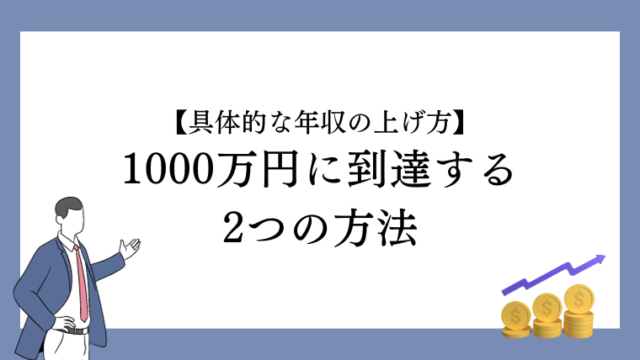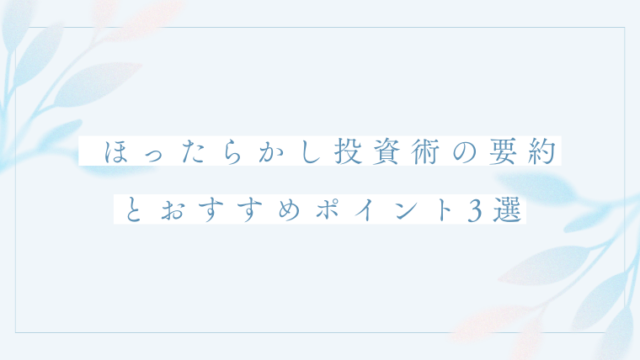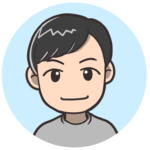ねぇパパ、仕事と家族だったらどっちが大事?
そるとちゃん、急にどうしたの(笑)
家族に決まってるでしょ。
そるとちゃんより大事なものは存在しないよ。
じゃぁ、健康と友人だったら?
うーん…友人ももちろん大事だけど、健康は全ての源だからね。
二択だったら健康かな。
ただパパは「健康と友人は金で買えない」から両方大事にしたいよ。
合格!パパはしっかり「エッセンシャル思考」出来ています!
(テストされてたんだ)
こんにちは!エッセンシャル思考の中でも「上手な断り方」はビジネスマンの必須スキルだと思っているあいろん(@iron_money)です。
今回は書籍「エッセンシャル思考」を読んで、要約6選と勘違いしがちな危険ポイント3選を紹介します。
この記事はこんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
エッセンシャル思考とは
パパ、そもそもエッセンシャル思考ってなんなの?
エッセンシャル思考の基本についてまずは紹介するよ。
書籍「エッセンシャル思考」は、2014年に著されたシリコンバレーのコンサルティング会社CEOのクレッグ・マキューン氏の著書です。
本書の伝えたいメッセージはとても明確です。
書籍内で頻繁に登場するメッセージは下記です。
「より少なく、しかしより良く」
上記の追求こそ、エッセンシャル思考の本質になります。
わたしが特に本書をすすめるのは、下記に該当するような方です。
「忙しい」人に向けて時間創出の考え方を説いている本なので、逆に時間のありあまる学生などではピンと来ないこともあるでしょう。
本書ではエッセンシャル思考をより良く伝えるために、20章に分けて展開されています。
すごい細かく章が分かれているんだね。
一例としてあげると、第8章のテーマは「睡眠」です。
睡眠に関する様々な内容が記載されています。
仕事はハードワークこそが美徳であり、「ランチは負け犬のもの」「睡眠は子供のもの」なんていう誤った仕事の価値観はそこにありません。
睡眠こそが優秀さの証であると本書は説いていきます。
上記のように各章ごとに展開されている内容から「万人に共通しやすい」「内容が活かしやすい」と感じた6点にポイントを絞って要約していきます。
エッセンシャル思考自体は非常に汎用性が高いんだけど、いきすぎたエッセンシャル思考が組織や個人に危険をもたらす可能性についてもパパは言及しているよ〜。
人生バランスが大事だよね。
エッセンシャル思考要約6選
わたしが「エッセンシャル思考」の中でも特に大事だと感じたのは下記の6点です。
- 選択
- ノイズ
- 孤独
- 洞察
- 拒否
- 前進
選択
「選択」の章では、下記の言葉から始まります。
「われわれを人間にするのは、選択する能力である。」
選択とは行動であり、与えられるものではなく「つかみとるもの」である。
言葉にすると当たり前すぎる「選択」の大事さですが、本書ではそれを手放してしまう理由として「学習性無力感」を挙げています。
仕事で努力をしても無駄という経験をすると、人間は2つのパターンに分かれるそうです。
努力をやめる人が褒められたものでないのは誰でもわかります。
しかし「仕事を引き受けすぎる人」は一般的には勤勉で働きものな印象を受けるでしょう。
著者に言わせると引き受けすぎるのは「選択肢を考えようとしていない」と同義であり、何かを選べば何かを捨てざるをえないという「トレードオフが理解できていない人間」という事になります。
何も選択せずに生きていることは、自分の人生を大事にしていないということと同じなんだね。
これは重要な考え方だね。
ノイズ
「大多数のものは無価値である」
ノイズについて述べている本章にも、ビジネスの本質が凝縮されています。
「努力は大切だ。だが、努力の量が成果に比例するとは限らない。がむしゃらに頑張るよりもより少なく、しかしより良く努力した方が良い」
著者は本書で上記のように主張しています。
至極当然の話に聞こえますが、どれだけの人が「より少なく、しかしより良く」を実行できているでしょう?
パパが今日の夕方に行おうと思っていた本記事の編集を真夜中に行なっているのはなぜでしょう?
すいませんとしか言えない…
上記は全部ノイズです。ノイズを遮断できず、あいろんは「記事の更新」という大事な予定が後ろ倒しになりました。
日常にありふれている「ノイズ」との付き合い方を再考させられる内容になっています。
「大多数のものは無価値である」っていう前提から考えると、確かに日々の行動って無駄が多いよね。
「時間がない」と思っている人ほど、一読する価値がありそうな内容だね。
孤独
「深い孤独がなければ、まともな作品はつくれない。」
上記はパブロ・ピカソが残している名言の一つです。
本章のテーマは「考える時間を取り戻す」であり、様々な偉人の例が紹介されています。
アイザック・ニュートン氏の例を見てみましょう。
ニュートン氏は万有引力の法則の論文執筆の際、2年間ほぼ引きこもっていたそうです。
そうして法則を発見した際、彼はこう答えたそうです。
「考え続けていたんだ。」
上記が並大抵の「考え続けていた」でないことは想像に難くありません。
また、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏も「孤独」の愛好者で知られています。
ビル・ゲイツ氏はどれだけ忙しさの最中にあっても必ず年に2回、1週間ほど下記だけのために仕事を離れるそうです。
ニュートン氏やビル・ゲイツ氏のようなスーパー偉人たちでさえ忙しさの合間を縫って時間を作っています。
自分程度が「忙しい」を理由に時間を作れていない事実に深く反省の意を感じた内容でした(笑)
「孤独」というより、「深い思考をする」ために1人になる時間は絶対必要だということがエピソードからよくわかるね。
洞察
「あらゆる事実には、本質が隠されている」
洞察の章では、情報の本質をつかみとるヒントを教えてくれます。
洞察のプロであるジャーナリストはどのように事実を拾い上げるか?という事例が、本書では下記のように記されています。
「単に情報を受け渡すだけなら、誰にでもできる。すぐれたジャーナリストは、情報の断片を調べ、それらの関係性を発見する。部分の集まりから全体像をつくりあげ、人々に通じる意味を付与する仕事だ」
「情報とは断片的ではあまり意味を持たないが、全体につながった時にはじめて意味を持つ」というのは確かにその通りです。
実際のビジネスにおいても洞察力に優れている人間は、仮説構築の筋が良くて話が面白いもんね。
拒否
パパがエッセンシャル思考で1番大事だと考えているのが、下記の「拒否」です。
「断固として上手に断る」
これは言うのは簡単ですが、実行するのは非常に難しいことです。
この章で私は、シンシアという女性のエピソードに強く強く胸を打たれました。
今でもことあるごとに読み返しています。
昔、シンシアの父親がサンフランシスコへの出張に連れて行ってくれた。
当時12歳だったシンシアは、父親との「デート」を数ヶ月前から楽しみにしていた。
プランは完璧だった。
父親の講演を最後の1時間だけ聞き、4時半に控え室で落ち合う。
誰にもつかまらない内に会場を出て、ケーブルカーでチャイナタウンへ向かう。
好物の中華料理を食べて、お土産を買い、観光して映画を観る。
それからタクシーをつかまえてホテルに戻り、プールでひと泳ぎ。
ルームサービスで生クリームたっぷりのホットファッジサンデーを頼み、気がすむまで2人で深夜のテレビを堪能する。
シンシアと父親はこのプランを念入りに話し合い、計画を立ててワクワクしていました。
ところが当日、トラブルが発生します。
講演会場を出ようとした時、父親の仕事仲間にばったり出くわしてしまったのです。
仕事仲間は父親に言います。
「埠頭に最高のシーフードを食わせる店があるんだが、一緒にどうだい?シンシアも一緒にね」
父親はこう返します。
「それはいいね。埠頭でディナーとは、最高だろうな」
父親の言葉を聞いた時、シンシアは心底意気消沈したそうです。今日は2人でデートの約束だったのに…と。
しかし、その後父親は続けます。
「でも今夜は駄目なんだ。シンシアと特別なデートの約束をしているものでね」
そういって父親とシンシアは再び歩き出し、予定通りにサンフランシスコで一生忘れられない夜を過ごしたそうです。
シンシアは絶対にパパと2人でデートしたかったから、ここで仕事仲間を優先されていたらたぶん一生根に持っていただろうね。
気持ちわかるなぁ。
上記に登場したシンシアの父親は、名著「7つの習慣」で有名なスティーブン・コヴィー氏だそうです。
娘のシンシアさんはコヴィー氏の死後に下記の通り語っています。
「この出来事のおかげで、父とのあいだには永遠に切れない絆が生まれました。父は私がもっとも大切な存在だと示してくれたからです」
コヴィー氏は娘を優先するという決断によって、いつまでも消えない思い出を娘にプレゼントしたということです。
私は上記を読んだ瞬間、雷に打たれたように痺れました。
コヴィー氏を深く敬い、尊敬します。
何があっても娘へ態度で示せる父親でありたいと強く感じました。
「拒否」によって本当に大事な時間を守るというパパの基本的思想は、エッセンシャル思考のコヴィー氏のエピソードを読んだ後に「自分もこんな人間でありたい」と考えてなったそうです。
パパが尊敬しているコヴィー氏の名著「7つの習慣」について、ざっくり知りたい方はこちらの記事もどうぞ♪
前進
「小さな一歩を積み重ねる」
当たり前のことながら、前進するためには他に方法がありません。
カナダのリッチモンド市の警察は「小さな一歩」によって犯罪率を大きく下げたケースとして本書で紹介されています。
リッチモンド市のウォード・クラッパム氏は若くして署長に就任し、それまでのやり方に疑問を投げかけたそうです。
「なぜわれわれは、犯罪が起こるまで待たなくてはならないのか?なぜそんなに受け身なのか?」
そしてクラッパム氏は「ポジティブ・チケット」と呼ばれる善行に対して警察から与えられる切符をスタートさせました。
ポジティブ・チケットは映画館やコミュニティーセンターに無料で入れる引換券にしました。
このリッチモンド市の型破りな取り組みは、10年後に青少年の再犯率が60%→8%に激減するという成果につながります。
本書では下記のように記しています。
「ちょっとした善行をほめるというクラッパム氏のやり方は、小さな成功を認めることの大切さを教えてくれる」
車にひかれそうになっていた少女を助けてポジティブ・チケットをもらった少年に、警官は切符と共にこう声をかけました。
「すばらしいことをしたね。君は立派なことのできる人だ」
少年は家に帰り、ポジティブ・チケットを飾りました。
何に引き換えるの?との母親の問いに少年はこう答えました。
「引き換えないよ。ずっと持っておくんだ」
ポジティブ・チケットが自己肯定感を引き上げて、少年の意識に良い変化をもたらしたんだね。
この少年のような「小さな一歩」が年間4万件、10年間積み重なった結果として再犯率が52%も減少したことに驚きを禁じ得ません。
これは、日本の警察も全国的に取り入れた方が良いのではと強く感じた内容です。
褒め文化はとても大事ですよね。
エッセンシャル思考が危険なポイント3選
- 効率重視
- 初心者
- 拒否
前述の通り、エッセンシャル思考は様々なポイントから「より少なく、しかしより良く」を考えていく思考法です。
この思考法は万人に使えますが、場合によっては少し極論になってしまう危険性もはらんでいます。
「エッセンシャル思考」で検索すると、「エッセンシャル思考 危険」がトップキーワードにあがってくるもんね。
個人的にエッセンシャル思考が危険な方向に傾いてしまう可能性のある3パターンについても、下記にて紹介します。
効率重視
「より少なく、しかしより良く」は考え方として非常に重要です。
パパは体感として、総じてZ世代の人はエッセンシャル思考が上手な割合が多い印象があるそうです。
幼少期からデジタル製品が身近にあり、「時短」や「効率」を無意識的に重視するライフスタイルだったためでしょう。
ただ、効率重視はいいことばかりではありません。
実際に「効率重視」にとらわれすぎて、苦労した部下がいました。
その部下はとても優秀で、仕事も早く覚えも良い仕事のできる人間でした。
しかしながら、やや「効率」に傾きすぎるあまり、下記のような傾向が目立ちました。
上記のギャップは効率重視が陥りがちな落とし穴です。
非効率を推奨するわけではありませんが、効率重視のタイプは長い目で見ると「可愛げとガッツがある」同年代の若手より伸びないケースがあります。
基本的に、多くの仕事は人と人が行うものです。
特に若い内は先輩や上司から任される仕事で「伸びしろの差が出る」という不都合な真実があります。
結局パパの部下は仕事がしづらくなってしまい、「自分はこんな職場にいる人間ではない」と言い残して退職してしまったんだよね。
そして次の職場でも同じようなトラブルを起こしてしまったそうだよ。
行き過ぎたエッセンシャル思考は危険だという良い例です。
初心者
「量が質を凌駕する」
私は個人的には上記の考えです。
効率化も良いですが、圧倒的な量の中からしか自分に合った質は探せないというのが持論です。
パパが好きな書籍「30代を無駄に生きるな」にも同じ考えが書いてあるよね。
上記の理由により、エッセンシャル思考の考え方は素晴らしいですが「初心者」や「初学者」には向かない思考法だとあいろんは考えています。
仕事に対して「効率を意識して〜」とか「エッセンシャル思考にこう書いてありますよ」なんていう若手がいたら、こいつは伸び悩みそうだなぁと正直思います(笑)
やっていく中で「自分なりに考える」のは大いに大歓迎です。
ただし、「やりもしないで質だけを追う」というのは現実的ではありません。
量をこなさないと、質に対する感度が働きません。
「効率」と「量をこなす」は別の考え方ですが、勘違いしがちなので注意が必要です。
拒否
前述の「エッセンシャル思考要約6選」内では、シンシアのエピソードに深く感動した「拒否」。
「拒否」は使うタイミングや相手によって大変危険なケースがあるので、注意です。
例えば、シンシアのエピソードでコヴィー氏は娘から一生語り継がれる絆を手にしました。
もしこの日、ばったり会った人を優先してしまっていたらどうなっていたでしよう?
もし判断を間違えて、シンシアを拒否していたら一生遺恨が残ったでしょう。
考えただけで恐ろしいです。
拒否の使い方はとてもシビアであり、勇気がいる行動です。
「とりあえず重要じゃないし、何でも断れば良いや」くらいの浅い理解だと、逆に長きにわたって生きづらくなる可能性すら秘めています。
「拒否」に限らず、本書の内容は「文化の違いや立場の違い」の考慮が求められます。
上記を理解して、自分なりに取り入れていく柔軟さがあってはじめて成り立つことは心に刻んでおくべきでしょう。
なんでもかんでも断れば良いってものでもないんだよね。
難しいなぁ。
「拒否」は選択を間違えるとその後の人生にも影響を及ぼすくらい、諸刃の剣だね。
ラップアップ
今回は書籍「エッセンシャル思考」を読んで、要約と勘違いしがちな危険ポイント3選を紹介しました。
刺さるポイントが多い良書ですので、是非じっくりと手に取ってみてください。
最後に一言。
パパもコヴィーさんを見習って、ちゃんとそるとをエスコートするんだよ♪
それではまた!