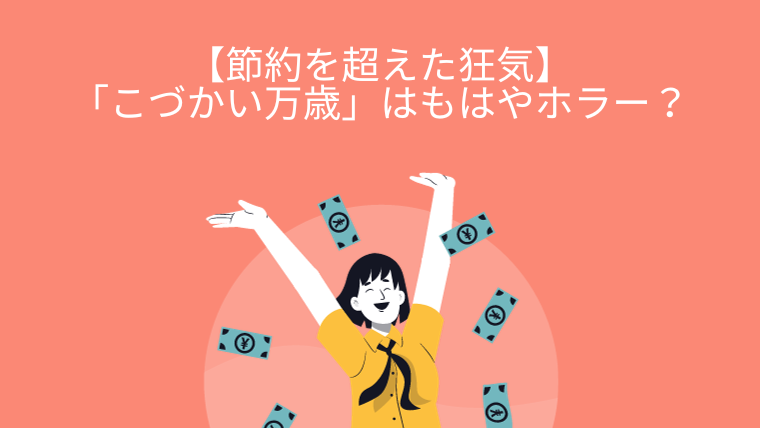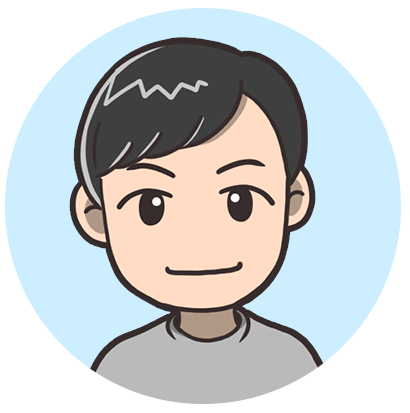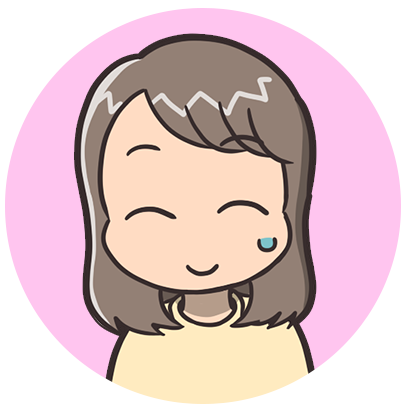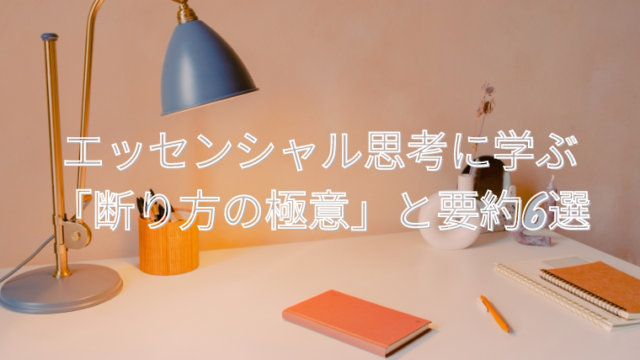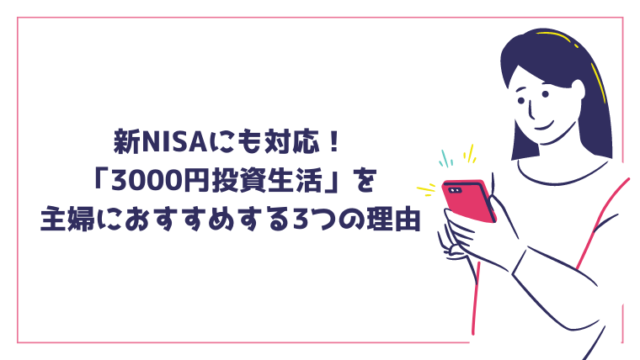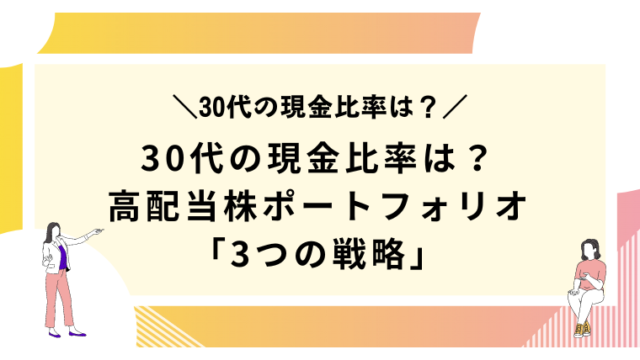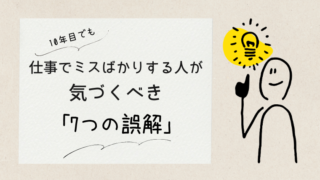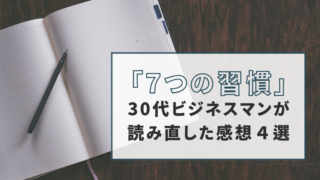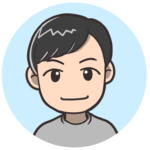パパが珍しく漫画読んでる~!何読んでるの?
吉本浩二さんが書いてる「定額制夫のこづかい万歳」という漫画だよ。
昔、アメトークでも紹介されてたマンガだよね♪面白い?
面白いんだけど、最近は節約の度を超えて「狂気的」「ホラー」と呼ばれることもあるんだよ(笑)
そうなの!?どんなエピソードなのか興味ある。
パパ教えて!
こんにちは!「自分もこづかい万歳にいつか登場したい」と目論んで応募しているあいろん(@iron_money)です。
今回は「狂気的なマンガ」とも形容される「定額制夫のこづかい万歳」を読んで感じたことを綴っていきます。
この記事はこんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
「定額制夫のこづかい万歳」とは

「定額制夫のこづかい万歳」は「おこづかい」を題材に色々な人間模様をあぶり出す、ちょっと珍しいドキュメンタリー漫画です。
2023年10月時点で単行本は第6巻まで発売されています。
舞台は埼玉県郊外、4人家族(奥さん+子供2人)で職業は漫画家の吉本氏。
幸せな一方で、子供にも生活にもお金がかかるのが悩み…ということで、月のおこづかい「21,000円」で生活しているそうです。
本書によると会社員の30~40代平均おこづかいが36,000~37,000円のため、平均より45%程低いお小遣いなんだよね。
そんな中、吉本氏は自身も含めて周辺でおこづかい生活をしている人のそれぞれに人間ドラマがあることに気づきます。
かくして、「おこづかいの使い方」からその人の価値観や人生を感じ取り、一話完結で人間ドラマを毎回お届けする本書のスタイルが確立しました。
作中で例を挙げるとキリがありませんが、おこづかい制の人物の一例を紹介します。
おこづかい制の人物の一例
吉本浩二氏(こづかい21,000円)作者
本マンガの作者兼主人公の吉本浩二氏。
月々のおこづかいは21,000円です。
お酒は飲まず、タバコも吸わず、ギャンブルもしない。
ただしお菓子とジュースが大好きで、マンガ内でも様々なお菓子を食べる姿が見られます。
50歳目前の身体であり、お菓子を食べまくる様子に対して奥さんが健康を心配している描写が多く描かれています。
- イオンのフードコートで仕事をする際の仕事のお供のコーヒーを真剣に吟味し、1リットル84円(税込)を購入(1巻より)
- 100円ショップの「お菓子4個で100円」から真剣にセレクト。「歌舞伎揚」「ポテトフライ」「いちご麦チョコ」「さくらんぼ餅」を選び、美味しくいただく(1巻より)
- 本マンガが読売テレビ「川島・山内のマンガ沼」に紹介されて15,000円の臨時小遣いが出た際、普段買えないお菓子を5,000円分大人買い(4巻より)
その他にも事あるごとにお菓子が登場するので、本書を読むとお菓子が食べたくなります(笑)
普段はあまりお菓子を食べないパパが、サッポロポテトを買ってきた時は本当にびっくりしました(笑)
筒木氏(こづかい20,000円)第3話登場
ママ友の筒木さんの旦那さんが第3話で登場しますが、凄腕のこづかい制です。
- 駅の駐輪代はこづかいから(なので遠くても歩く)
- 「業務スーパー」38円のお茶を買いだめして会社へ持参することで自販機の1/4の費用に抑える
- 予算1,000円くらいでやる晩酌が最高の楽しみ。ローソンで130円のやきとりを2本買い、キリンラガービールロング缶(238円)
毎話ごとに上記のような様々な小遣い制の人々のお金の使い方を通じて「人生模様」を見れるところが本マンガの最大の見どころです。
こづかい万歳が「狂気的」と思えるエピソード
パパ、普通に面白いだけで全然狂気が感じられないんだけど…
そうだよね。
ただ最近は1話ごとに毎回1人のエピソードが語られることが多くて、時々ヤバい人が出てくるんだよ(笑)
中でも、最近「狂気的」「ホラー」としてネット界隈を震撼させたのは「会社推し」の大石さん(32歳)です。
大石さんのエピソードをまとめると下記になります。
- おこづかいは月に2.3万円(社食費込)
- 会社が大好きな「会社推し」
- 社歌を通勤時に聴く
- こづかいは会社の自分のデスク周りのガジェットにほぼ突っ込んでいる
- 会社に寝泊まりする時多数
- 休みが続くと会社に行きたくてソワソワする
仕事が好きなのは素晴らしいことですが、「社歌を聴きながら通勤」「コロナで通勤できなくて泣きながら疑似通勤する」など、常人では中々理解できないエピソードが満載です(笑)
X(旧Twitter)でもネタとして取り上げられているくらい、賛否両論があったお話なんだよね。
パパ曰く、毎話ではないにしろ各巻に1-2名は上記のような「共感できない人」が登場するらしいよ。
ただ、上記のような話はネタとして読めばシンプルに面白いです。
他には感動させられるようなエピソードも多数存在しているので、構成としては特に違和感を感じるものではありません。
「お金と幸福」について考えさせられる
前述の通り、「こづかい万歳」には様々な人々の人間模様が泥臭く描かれています。
「おこづかい」を通じて、下記が全く人により違うところに、本マンガの面白さがあります。
「歌舞伎揚」も「ローソンのやきとり」も「キリンラガービール」も大人であれば、さほど意識もせずに買えるくらいの値段です。
ただ、上記が買えるから前述の登場人物に「幸福度」で勝てるとは限らないのが面白いポイントです。
制限がある中で自分で「おたのしみ」として盛り上げに盛り上げて食べるから、美味しさもひとしおなんだね。
全体的に小学生が通う「駄菓子屋」に通ずるマインドがあります。
限られたおこづかいで最大限の満足度にするためにどれだけ悩み抜くかという考え方です。
資本主義経済下において、お金は単なる「交換手段」に過ぎません。
お金持ちが必ずしも幸福とも限りません。
所得も総資産も一定のラインを越えたら幸福度とは比例しなくなることが、研究結果でわかっているんだよ。
限られたおこづかいの中から真剣に人生の生きがいや楽しみを見つける各登場人物のさまざまな事例にはハッとさせられる時があります。
パパ的には、楽しく読めるマンガでありながら「幸福論」が詰まっている哲学書だと感じているそうです。
本書は「アメトーーク」はじめ様々なメディアで取り上げられて人気が出ました。
題材は地味ですが、今後も著者の吉本浩二氏にはスタンス変わらず細々と続けて欲しいと一ファンとして切に願います。
印象的なエピソード2選

前述の通りヤバめのエピソードもあるこづかい万歳ですが、頻繁に登場する吉本浩二氏の奥さんのエピソードはパンチが効いていて面白いです。
奥さんのエピソードはちょっと笑えるものから、感動的なものまで幅広いのが特徴です。
奥さん関係のエピソードで非常に印象的なものを2点ほど紹介します。
「日高屋」でストレスを発散
吉本浩二氏のおこづかい21,000円より圧倒的に少ない「7,000円」のお小遣いで暮らしている奥さんですが、ドケチでお金を使わず楽しめる天才だそうです。
- 調理器具は独身時代に100円ショップで買ったものをボロボロになるまで使い続ける
- 携帯ゲームは「風船にボールを当てるヤツ」だけを無料で4年以上楽しむ
- 子どもにメガネを折られても、ボンドでくっつけて使い続ける
奥さんは吉本氏と違い、お酒が大好き。
毎日の晩酌を楽しみに生きています。
そんな奥さんはこづかいをラーメン屋「日高屋」で使うそうで、楽しみ方が下記の通り紹介されています。
- 生中ジョッキ(税込290円)※消費税10%になってもお値段据え置き
- 餃子(税込155円)
- 味付玉子(半額券使用)
- レモンサワー(税込290円)
奥さんにとっては大体1,000円程度でリフレッシュできる最高のストレス発散だそうです。
1人で日高屋に入って「せんべろ」して帰れるとはすごい。
わたしもやってみようかな(笑)
給付金の使い道でホッコリ
2020年に「国からのおこづかい」給付金が出た時のエピソードです。
4人家族で合計40万円が出た吉本氏は、早速お金をおろして家族会議に向かいます。
しかし、せっかくの臨時収入も下記に消えていきます。
今まで給付金を「使うこと」しか考えていなかった吉本氏。
奥さんに「家や子どものことばかりで、自分の欲しいものはないの?」と質問します。
奥さんはこう答えました。
「いつも通り私は日高屋で飲めれば、それでいいのよ」
この言葉とともに、物欲しそうな吉本氏に勘づいた奥さんは臨時ボーナスの21,000円を渡します。
なんて素晴らしい奥さんなんだと、ほっこりしたNo. 1エピソードでした。
この一連の行動に感動した吉本氏は、家族を日高屋へ紹介します。
おこづかいで家族と奥さんに食事とお酒を振る舞い、楽しいひとときを過ごしました。
上記のエピソード、特に奥さんの言葉には心が震えました。
出来事としては「ただ給付金をもらって、日高屋に食べに行っただけ」の回なのですが、お金と幸せについて奥さんに教えてもらいました。
上記の話は第二巻に収録されているよ〜♪

ラップアップ
今回は「狂気的なマンガ」とも形容される「定額制夫のこづかい万歳」を読んで感じたことを綴っていきました。
時に狂気的なエピソードもありながら、ほっこりも出来て面白い漫画ですよ。
最後に一言。
「おかねの使い方」の考え方を学べるのでとても面白いよ♪
ぜひ読んでみてね♪
それではまた!