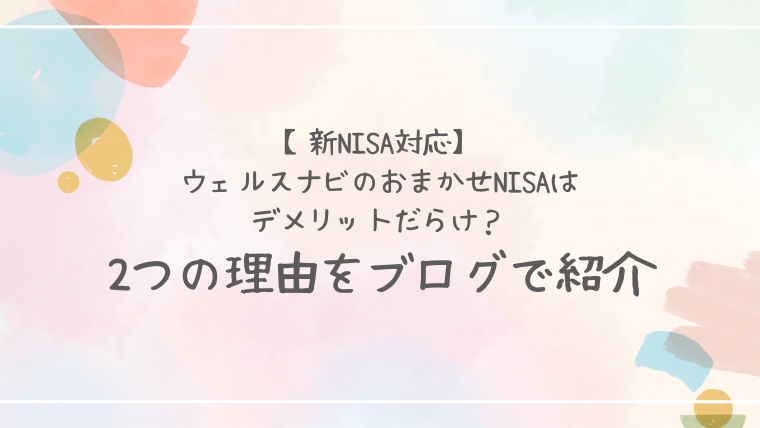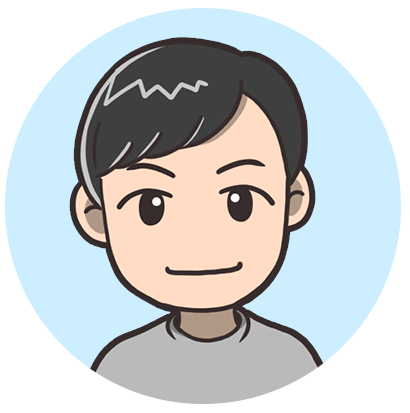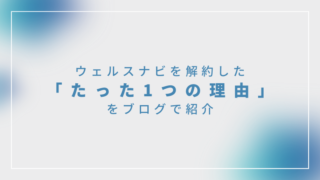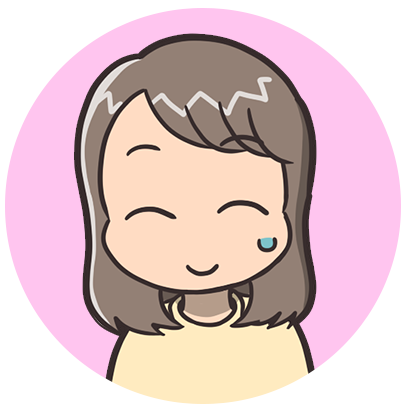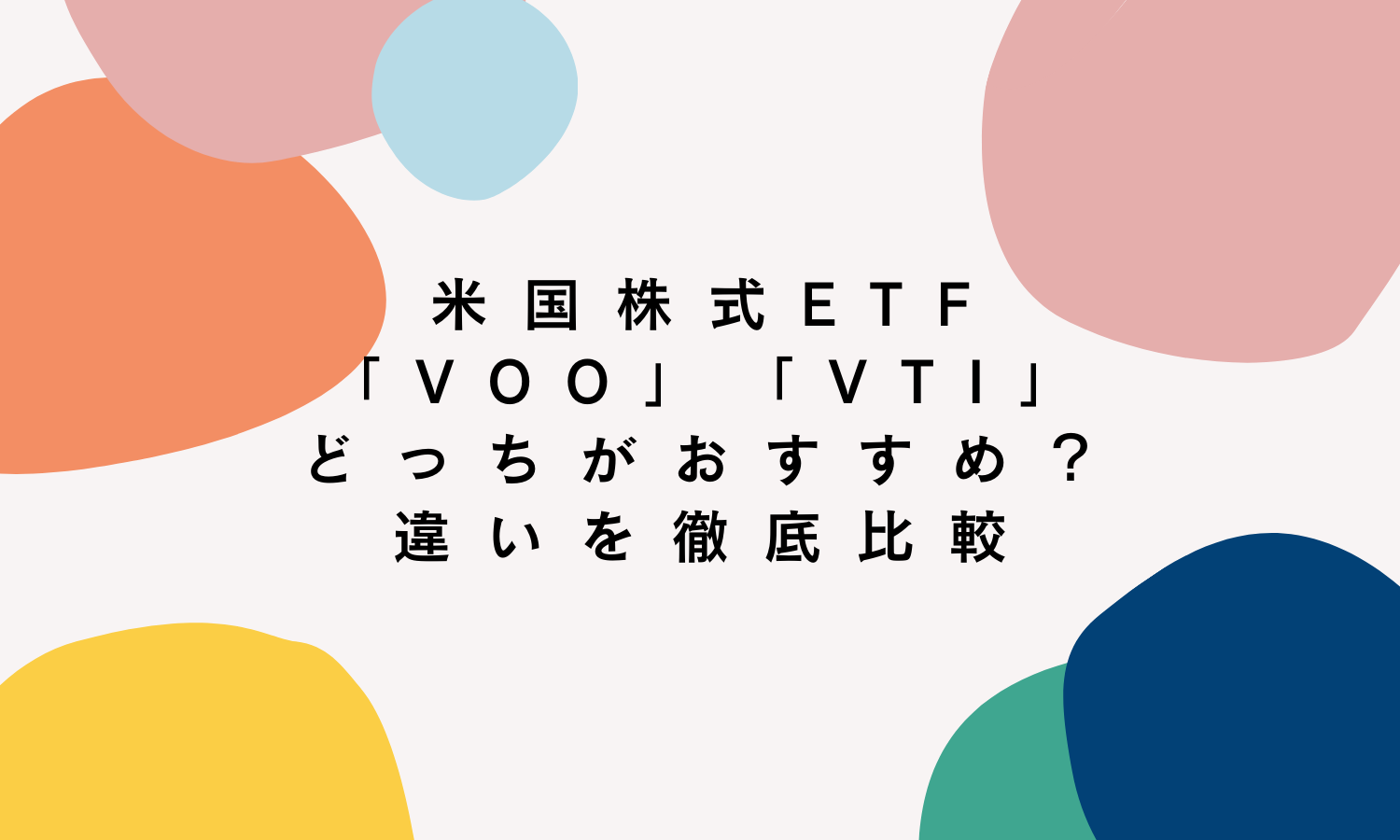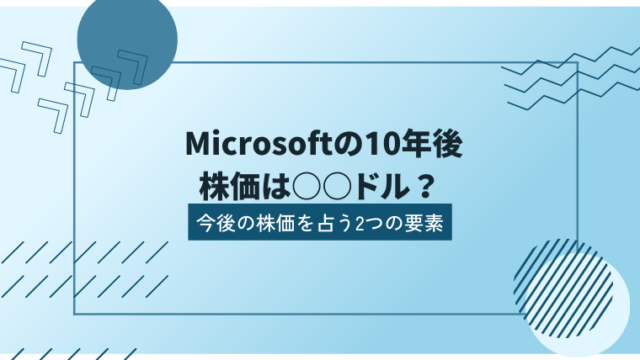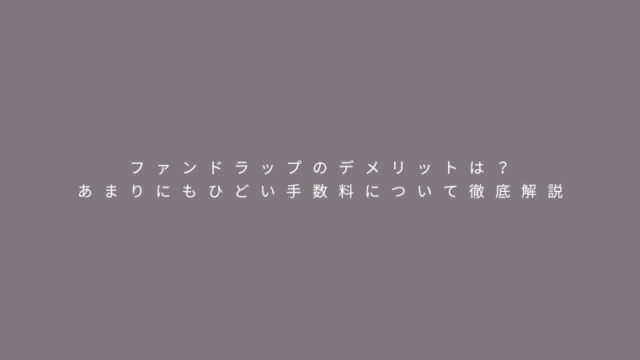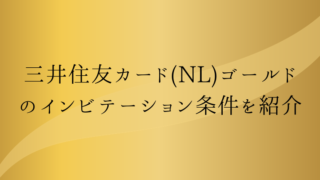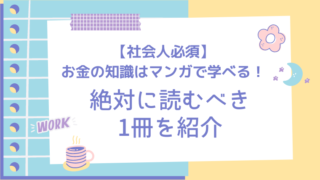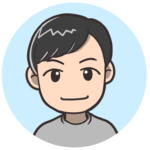パパ、友達のお父さんが検討しているらしいんだけど、新NISAにも対応しているウェルスナビの「おまかせNISA」ってどう思う?
そるとちゃん、悪いことは言わないから辞めておいた方が良いよ。
投資初心者には想定できないデメリットが多すぎる。
え、そうなの?
なんでブログで紹介してないのよ(怒)
パパの記事を友達のお父さんに見せるから早く書いて!
はい、すいません。
じゃあおまかせNISAをおすすめできない理由を書きます。
こんにちは!新NISAはおまかせにしない方が良いと思っているあいろん(@iron_money)です。
今回はWealthNavi社がサービスを提供している「おまかせNISA」について、おすすめできない理由とデメリットについて紹介します。
この記事はこんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
「おまかせNISA」とは
おまかせNISAはWealthNavi(ウェルスナビ)が提供している「日本初、NISA口座で自動でおまかせの資産運用」サービスです。
ウェルスナビのホームページから抜粋すると、下記の通りです。
- 世界水準の「長期・積立・分散」投資を「おまかせ」で行うことができる
- 新NISAにも対応している
- 積立と一括どちらでも対応できる
また、下記のように特徴が記載されています。
- 特徴①利益に税金がかからない
- 特徴②約50カ国11,000銘柄に分散投資
- 特徴③難しいことは自動でおまかせ
おまかせNISAに興味を持つ層は、自動でおまかせの点が魅力的に感じるんだろうね。
おまかせ=自分で判断できないということだからね。
これが良く理解せずに投資して損失を被る重大な落とし穴につながるんだよね。
現在「おまかせNISA」で検索をすると付随する関連ワードに「デメリット」や「評判」が並びます。
これはどういうことなのか、考察していきましょう。
前提として、パパはウェルスナビへの投資は「条件付きアリ」派です。
過去記事に詳しく書いてあります。
しかしながら、今回の新NISAに対応した「おまかせNISA」についてはナシ派です。
その理由を紹介していきます。
おまかせNISAのデメリット2選
おまかせNISAのデメリット2点は下記の通りです。
- 手数料の高さ(税込年率1.1%)
- NISA枠が複雑なポートフォリオになる
それぞれ解説していきます。
手数料の高さ(税込年率1.1%)
「おまかせNISAを使う必要がない」最高にして最大の理由は、コストです。
手数料が税込で「年率1.1%」はどんなに素晴らしい仕組みだろうと、個人的には検討に値しません。
高すぎです。
年に1.1%の手数料は、運用資金に応じて下記の金額が確実に発生します。
| 運転資金に応じた手数料額 | |
|---|---|
| 運用資金100万円 | 手数料1.1万円/年 |
| 運用資金1,000万円 | 手数料11万円/年 |
| 運用資金3,000万円 | 手数料33万円/年 |
| 運用資金5,000万円 | 手数料55万円/年 |
確かに、金額が少ない内は気にならないけど運用資金が増えると無視できない金額だね。
パパが基本的に投資している投資信託やETFの目安「0.1%以下」と比べると一目瞭然だね。
数千万円単位で資産を運用する規模になると、数十万円の差が出ちゃうもんね。
運用資金が少ない時はまだしも、資産が増えてきた時のインパクトは大きいものになってきます。
NISA枠が複雑なポートフォリオになる
ウェルスナビの「おまかせNISA」ホームページには、下記のような記載があります。
- つみたて投資枠・・・0%
- 成長投資枠・・・年率最大1%
- 新NISA口座に自動積立だけで入金した場合・・・年率0.63〜0.67%
- クイック入金や振込入金を利用した場合・・・年率0.7〜0.1%
※自動積立を利用した場合、リスク許容度レベルごとに定めた割合で「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方で資産を購入します
リスク許容度別の資産購入割合は、下記のとおりです。
| リスク許容度別の資産購入割合 | ||
|---|---|---|
| リスク許容度1 | つみたて投資枠10% | 成長投資枠90% |
| リスク許容度2 | つみたて投資枠20% | 成長投資枠80% |
| リスク許容度3 | つみたて投資枠30% | 成長投資枠70% |
| リスク許容度4 | つみたて投資枠33% | 成長投資枠67% |
| リスク許容度5 | つみたて投資枠33% | 成長投資枠67% |
なんか手数料とか枠別に色々なパターンで分かれているんだね。
難しいね。
その通り!
大体にして「つみたて投資枠」は年間120万円(総額600万円)まで定められているから、月10万円以下であればわざわざ成長投資枠に投資する必要ないんだよ。
つみたて投資枠でオルカンとかS&P500に一回「積立設定」してしまえば簡単に出来るもんね。
それなのに、わざわざ上記のように複雑な体系にしているということは…
おそらく、ウェルスナビも手数料がないと困っちゃうから上記のような設定にしているんだろうね。
NISAの枠は、1つの金融機関でしか開設が出来ません。
すなわち、ウェルスナビにNISA口座を開設した時点で下記の状態を受け入れることになります。
パパ的にはウェルスナビを使いたい場合は「特定口座」で運用してみて、内容を理解するのがファーストステップだそうだよ。
投資の基本は「わからないものに投資しない」です。
わたしもあまり詳しくないですが、個人的にはパパの言うとおりネット証券で自分で積立設定する方がはるかに納得感があります。
ラップアップ
今回はウェルスナビがサービスを提供している「おまかせNISA」について、おすすめできない理由とデメリットについて紹介しました。
短絡的におまかせNISAを利用した挙句「こんなハズじゃなかった!」とならないように判断の一助として頂ければ幸いです。
最後に一言。
投資は自己責任。
自分が理解できてないのに、おまかせして良いことなんて1つもないので注意しましょう。
それではまた!