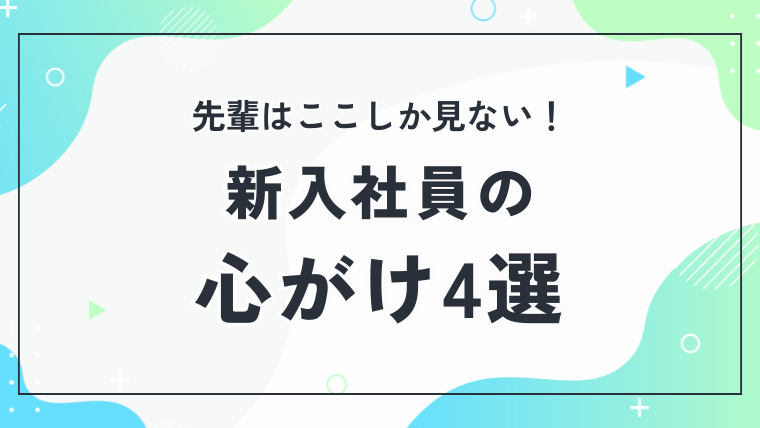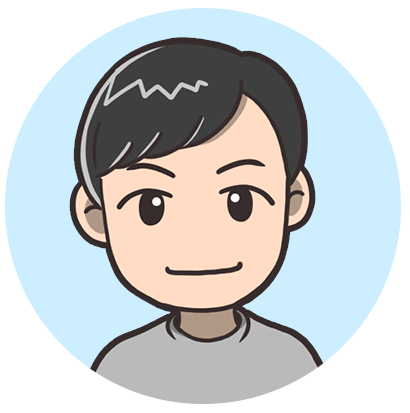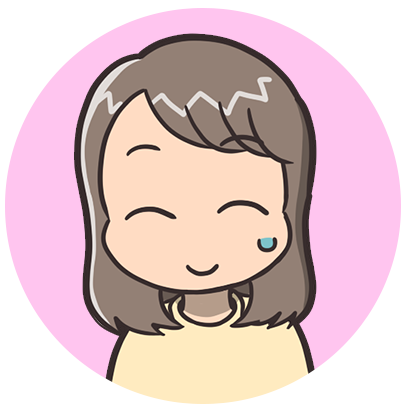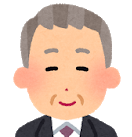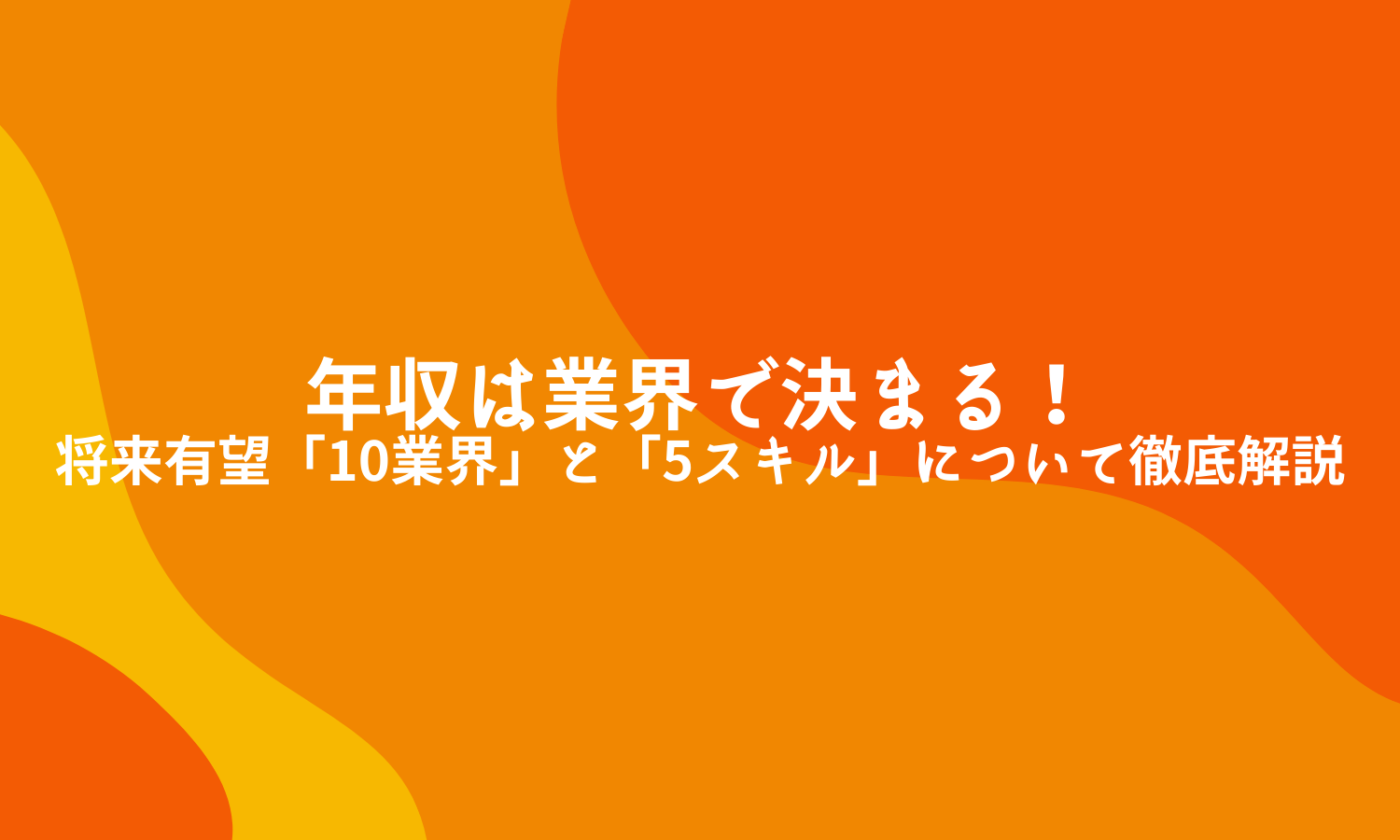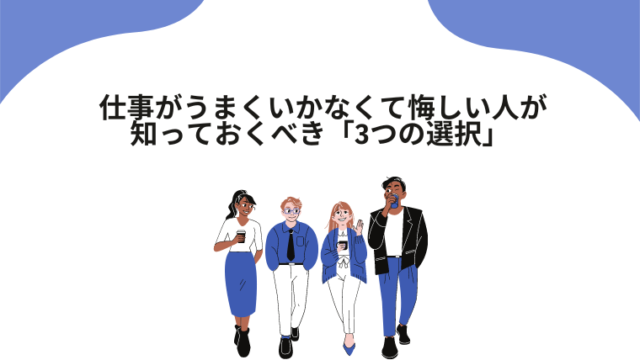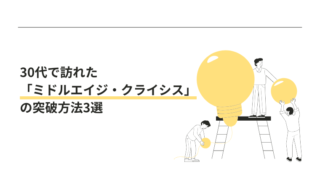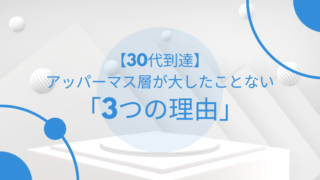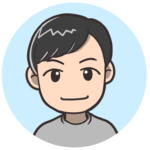最近、会社の新人が「挨拶しない」ってちらほら聞くよね。
パパの会社はどう?
そるとちゃん、部長みたいな質問だね(笑)
うちの会社はみんな挨拶してくれるよ。
正直、それだけで80点くらいは合格だよね。
「挨拶」「偉そうな態度を取らない」「師匠を早く見つけてひたすら真似する」新入社員はこの3点だけ出来ればOKだもんね♪
パパよりそるとちゃんの方が、上司に向いてるかも(笑)
こんにちは!結局は「素直さ」が1番大事という真理を知ったあいろん(@iron_money)です。
今回は、新入社員が軽視しがちで先輩社員が必ず見ている「視点」を紹介します。
この記事は、こんな方に向けて書いています。
結論としては、新入社員の心がけ4選は下記になります。
- 挨拶をする
- 偉そうな態度を取らない
- 師匠の真似をする
- ①〜③を何があっても継続する
それでは早速いってみましょう!
これだけは大事!新入社員が絶対に心がける項目4選

①挨拶をする
いきなりですが新人が一目置かれる存在になる、魔法の言葉を授けましょう。
「おはようございます」
「こんにちは」
「お先に失礼します」
「ありがとうございました」
これだけです。
これを、やり続けましょう。
そうすれば、相手はきっと貴方に好印象を持つでしょう。
「そんなことか」
「わざわざ言われなくたってわかってるよ」
新入社員の皆さんの、呆れた声が聞こえてきそうです。
しかしながら、挨拶の本当のパワーを理解している新入社員はほぼ皆無でしょう。
挨拶を「し続ける」って、意外と難しいよね。
先輩たちも出来ていないからね(笑)
配属初日や節目のタイミングで挨拶をする事は、誰でも出来ます。
しかしながら、仕事は毎日の出来事です。
上記でも、淡々と挨拶し続ける事は立派なスキルです。
試しに、入社後の最初の一ヶ月で社内を観察してみてください。
「挨拶」が出来ていない先輩が目につくでしょう。
上記は先輩になったからではなく、単純に挨拶が出来ない人なのです。
ちなみに、パパは新入社員の時フルパワーで全員に挨拶していたらしいよ。
これはこれで半分正解なのですが、その内に疲れてしまいます。
続かなくなるのであまり万人におすすめ出来ません。
別に大きい声でなくても良いので、お世話になったり関わっている人には個別に挨拶をしていきましょう。
半信半疑のあなたは、インターネットで「新入社員」と検索してみましょう。
関連キーワードですぐに「新入社員 挨拶しない」と出てきます。
それだけ先輩たちは気にしている、ということですね。
この視点、地味に大事なので覚えておいて損はないです。
私の職場に、誰にでも必ず挨拶をする好印象の青年がいます。
彼は、数年で若手エースとして頭角を現し「無双状態」を作り上げました。
パパは、その後輩を見て「挨拶は令和の時代でも通用するスキル」だと逆に教えられたそうです。
②偉そうな態度を取らない
前述の通り、挨拶はとても大事です。
しかしながら「挨拶はしているのに、いまいち周りからの評判が良くない」という新入社員も一定数存在します。
そんな時、考えられるのが「偉そう」に映ってしまっていることです。
「新入社員 え」で検索をかけると、「偉そう」がTOPに表示されます。
それほど、先輩たちの勘に触るキーワードとなっているんだね(笑)
パパが言われた中で、具体的なキーワード一例を出してみます。
「それはわかってるんですけど」
「大体わかりました」
「効率悪くないですか?」
「意見を言う」と、「偉そう」の境界線が理解できていない人が多い印象です。
パパも新入社員の時、上記のような感じでした(笑)
生意気を履き違えていたと今では思うそうです。
上記は、言い換えと言い方で柔らかく変化させることが可能です。
- それはわかってるんですけど→「〜までは理解ができたのですが、この部分が曖昧で…すみませんがもう一度確認してもよろしいでしょうか」
- 大体わかりました→「ありがとうございます、私でも理解できました。わかりやすいお話ありがとうございました」
- 効率悪くないですか?→「ここの部分なんですけど、こういう考え方でやってみても良いですか?」
「能ある鷹は爪を隠す」
この言葉を胸に、謙虚な姿勢を忘れずに接しましょう。
虚勢を張らずとも、仕事が出来ると認めさせることは可能です。
③師匠の真似をする
「この人、仕事が出来る」
「この人みたいな仕事の進め方したい」
「この人のプレゼン、聞き惚れちゃうくらい上手いから真似したい」
社内でも社外でも良いので、師匠的存在を見つける事は重要課題の一つです。
イメージとしては、2-3人くらい見つけられると最高です。
私の場合、師匠の「服装」や「持ち物」、「間合い」や「言葉遣い」まで全て完コピできるようにしました。
完コピして続けていると、嫌でも慣れてきてオリジナリティが出てきます(笑)
今や先輩側のパパ曰く、師匠だと思われて、悪い気がしない率は100%だそうです(笑)
それくらいお互いにWin-Winの話だそうです。
師匠の存在は自分の将来を測る時、参考になります。
私も20代の頃は師匠たちに飲みに連れて行ってもらい、下記のような質問攻めにしていました。
言葉で確認するのは、超重要です。
チャットやリモートワークで同じこと聞くより、「リアルかつオフ」の場で聞く良さもあります。
今はインターネットを通じて誰とでも繋がれる世の中です。
ただあえて同じ社内や取引先に「ご縁」を感じ、師匠を見つけて越えるために頑張ってみる。
そんな泥臭い考え方が出来る新入社員は、先輩から好かれること請け合いです。
①〜③を何があっても継続する
社会人になると、否が応でもわかる事実があります。
それは「継続」の難しさ。
①〜③が最初は出来ていても、すぐに出来なくなる新人が大多数です。
そんな時、先輩や会社はどんな対応をするでしょう?
「あいつは挨拶しなくなった」
「最初は猫かぶってただけで、偉そうなやつだ」
「先輩みたいになりたいとか言ってたけど、口だけだったな」
上記を思うだけで、表面上は変わらず付き合ってくれる人が大半でしょう。
しかしながら、内心では評価が下がっていきます。
逆に、継続し続けるだけでどうでしょう?
「あいつは若いのにちゃんとしている」という、手にすると便利なレッテルを入手できます。
継続は力なり、再確認しましょう。
出来たら行いたい、新入社員が心がける項目
気負いすぎない
やる気満々の新社会人が重要な事実。
それは、「肩の力を上手に抜こう」というアドバイスです。
パパは気負いすぎた結果、精神面を病んでしまう同僚や後輩を何人も見てきました。
競走馬でいうところの「かかりすぎる」状態は、皮肉なことに優秀な人ほど陥りやすいです。
そして、「続かない人」の特徴的な性質でもあります。
やる気に満ち溢れた若者に、冷や水をぶっかけるような話です(笑)
ただ、知識としては覚えておくべきです。
入社直後は同期や年の近い先輩と比較して落ち込んだり、競争意識で頑張りすぎたりしがちです。
しかしながら、仕事人生は思っているより長丁場です。
時間軸を意識しないと、中年に差し掛かる頃にガス欠します。
若い内にガッツリ働いて、ビジネス基礎体力を上げることに対してパパは肯定派です。
ただやりすぎは注意だね。
気負い続けることは、無理をし続けている事と同義です。
無理は、心の病に繋がりやすいという意識を持ちましょう。
上記を知っているだけでも、心のリミッターのブレーキが効きやすくなりますので覚えておいて損はないです。
全ては健康から…です。
そして会社が教えてくれない、残酷な現実をもうひとつだけ教えます。
精神を病んで働けなくなっても、会社は面倒を見てくれません。
面倒を見てくれるのは、家族や本当に自分のことを想ってくれる人間だけです。
自主学習の意識を持つ
社会人になると、仕事以外の予定は自分で選択できます。
しかし、自分のキャリアをオススメしてくれる人は、待っているだけではまず現れません。
今までは何も考えなくても、生きていけた。
でも、結局は自分の人生だと良くも悪くも痛感するのが新社会人の特徴です。
したがって、自分を律する意識が大事です。
具体的な例を挙げてみます。
勉強じゃなくても、ハマって徹底的にやればそれは自主学習と同義です。
強制的にルーチンに落とし込んででも、自主学習はやるべきです。
10年後、その経験が血肉になります。
複数人の話や態度を基に判断する
新社会人は、産まれたばかりのヒナみたいなものです。
最初に接する部署・先輩の影響を、多分に受けます。
もちろんその人が前述の「師匠」に当たれば最高ですが、そんなケースばかりではありません。
まずは色々な先輩と接して考え方に触れ、自分なりの善悪や正義を持つ事はとても重要です。
頭でっかちにならず、複数の考え方を自分なりの仮説に導けるようになること。
これで、仕事の進め方がぐんと楽になります。
理想を持ちすぎない
「理想を持ちすぎるな」
これは、私が実際に師匠(当時の役員)から言われた言葉です。
パパは体育会系で猪突猛進だった事もあり、仕事に邁進してやる気はありました。
ただ、最初の仕事は苦手な「調整事項」ばかりで苦戦していた時期がありました。
自分は正しいと思っている話が通らずひっくり返され、苦労した時期もありました。
下記は、その時に師匠(関西弁)から言われた言葉です。
あいろんは理想を持ちすぎや。頭でっかちすぎる。
もっと地に足つけて歩かんと、誰もおまえについていかへん。
相手には、相手の立場がある。
理想の形は立場の数だけあるし、違う可能性もある。
あいろんは「話す」前に「聞く」クセをつけた方がええな。
自分の考えた通りに進まない物事にイラだち、余計に進まないという悪循環。
こんな私の状況を、師匠は見てくれていたのでしょう。
耳の痛い話だった事をよく覚えています。
今では、サラリーマンとしての必須スキル「社内調整」はパパの得意項目になっています(笑)
うまくいかない時は理想主義者になっていないか、振り返ってみましょう。
仕事の楽しさを見つける
仕事が出来る人は、どの部署でも楽しそうに仕事をします。
仕事が出来ない人は、どの部署でも辛そうに仕事をします。
これは色々なサラリーマンを見てきて、たどり着いた真理です。
この差はなんなのでしょうか?
仕事が出来る人は、「仕事の楽しいポイント」を見つけるのが上手です。
仕事が出来る人は、クレーム処理だろうが地味な仕事だろうが自分なりのやりがいを見つけ、KPIに落とし込む事に長けています。
だからこそ、成果が上がるとも言えます。
希望の部署・興味のない部署・色々あると思いますがどんな仕事にも面白みはあるものです。
そこを見つけられるようになると、サラリーマンとしての宿命「人事異動」にも前向きにいられるのでオススメスキルです。
是非この仕事の楽しさってなんだろう?と考えてみてください。
ラップアップ
今回は意外と新入社員が軽視しがちで先輩社員が必ず見ている「視点」を紹介していきました。
「どれも当たり前の話ばかりじゃん。方法論を教えて欲しい」と思ったそこのあなた。
思考法を習得できれば、方法論なんて後付けでどうにでもなります。
千里の道も、まずは心構えから!
共に日本経済を盛り上げていきましょう!
仕事って、出来る様になってくるとめちゃくちゃ楽しいからだまされたと思って出来る様になってみるところまでいってみましょう。
それではまた!