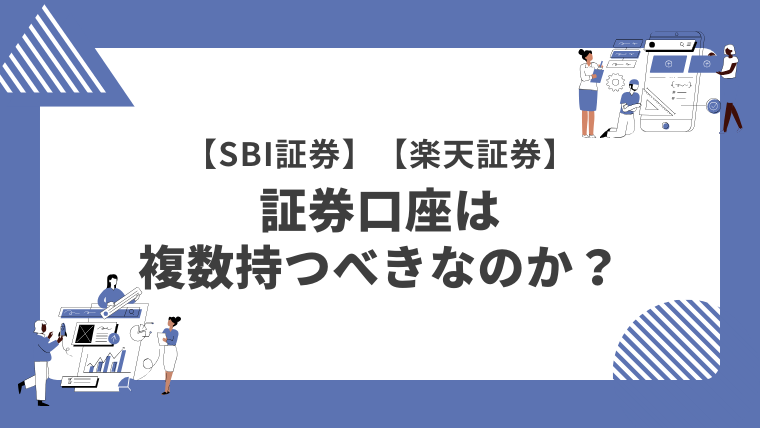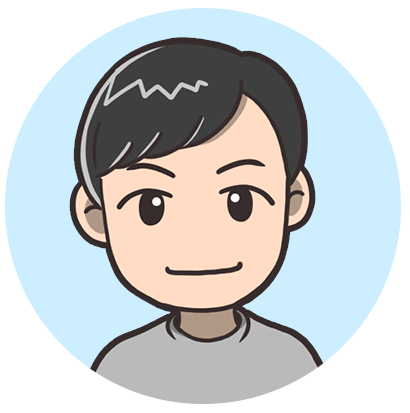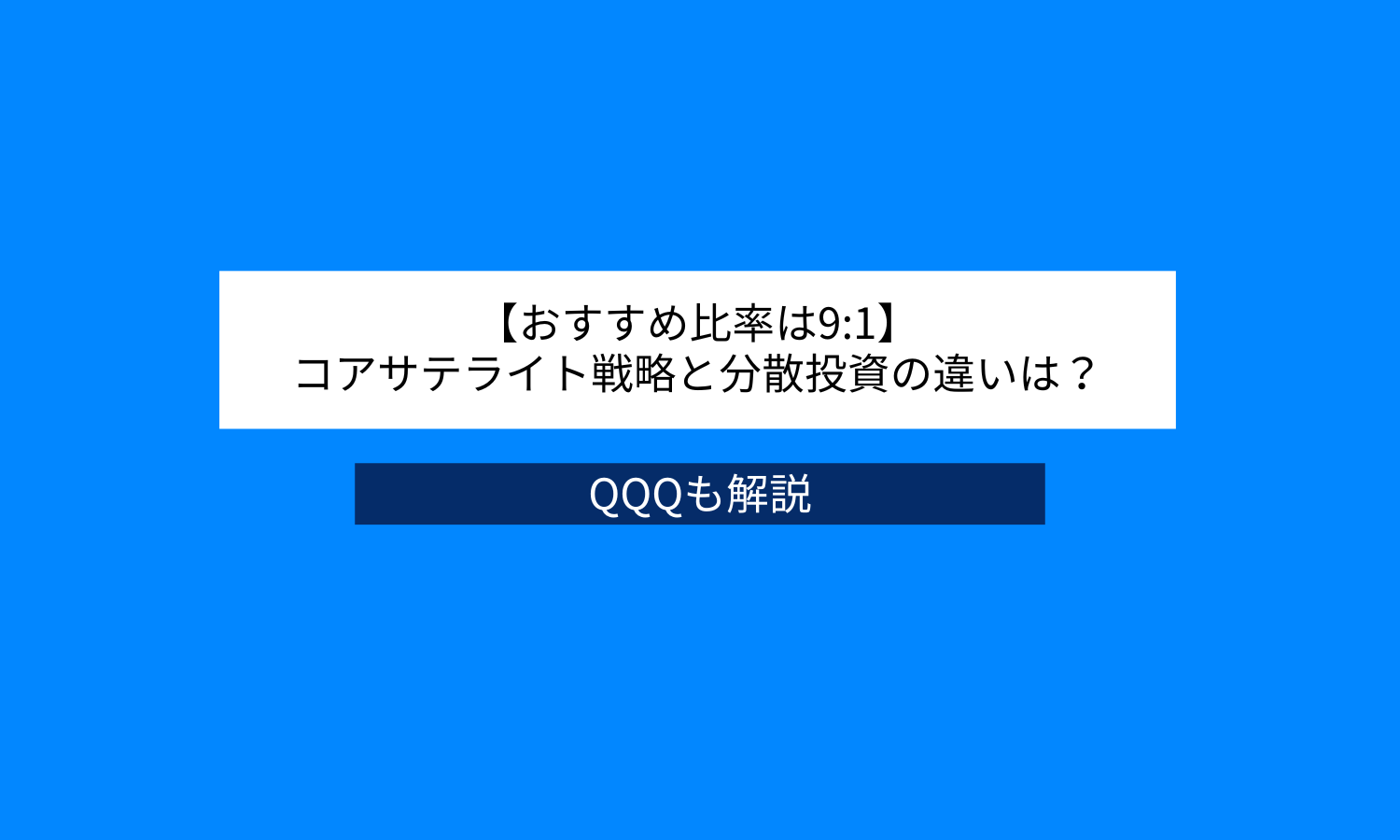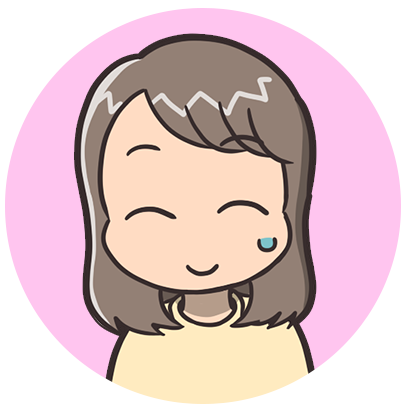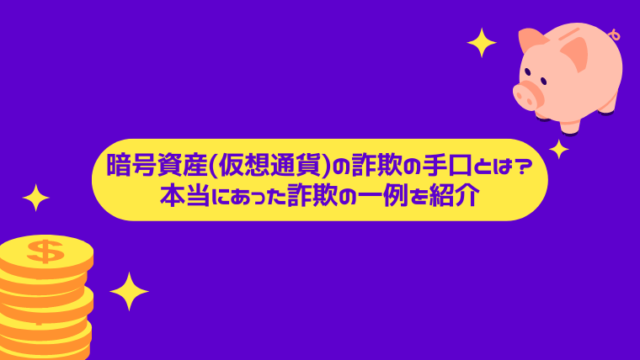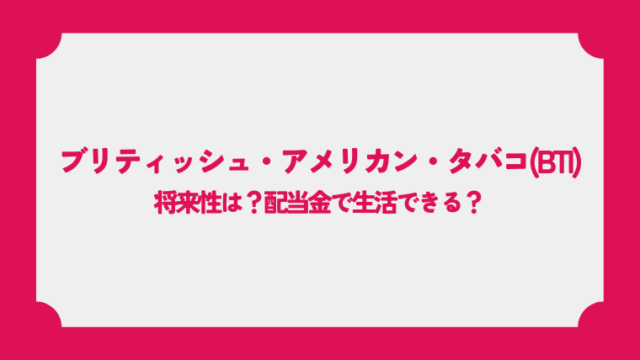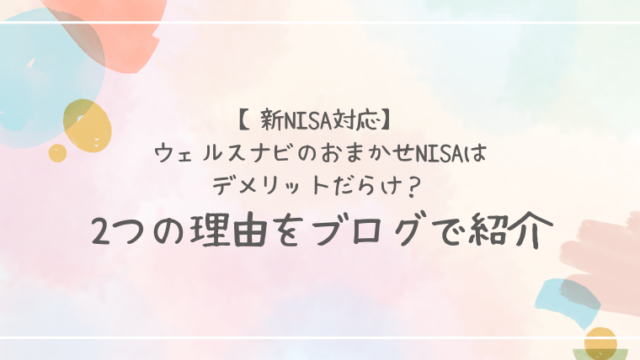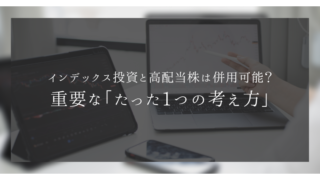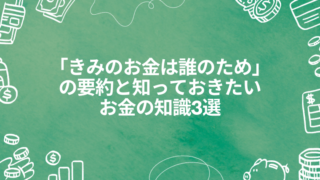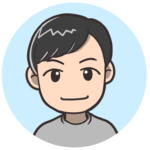パパ〜、証券会社って2つ以上持っている意味あるの?
パパは「SBI」と「楽天」をよく使っているよね。
それぞれに特徴があるからね。
パパはメインがSBIでサブが楽天、っていう感じかな。
あとクレカ積立もしているからマネックス証券も一部使っているよ。
2つ以上の口座を持っておくと色々な場面で使い分けが出来るから、おすすめだよ。
じゃあ、「おすすめの使い分け」をそるとにもわかるように教えてください♪
こんにちは!総資産が1,000万円を超えた辺りで複数の証券口座を使い始めた男、あいろん(@iron_money)です。
今回は「証券口座を複数持った方が良い場合」について考察していきます。
今回の記事はこんな方に向けて書いています。
結論としては、下記になります。
それでは早速いってみましょう!
証券口座を複数持った方が良い人、まだ持たなくて良い人
パパ、証券口座を複数持つと言っても全然お金ないのに分けてもあんまり意味ない気がするよ。
いい質問だね。
その通りで、ある程度の条件をクリアしないと口座が複数あっても意味ないんだよね。
その辺りを解説していくよ。
本記事では「証券口座の使い分け」をおすすめしますが、前提としてまだ複数口座を持たなくて良い人との境界線を先に紹介しておきます。
- 金融商品保有数が少ない
- 総資産が少ない
- 投資できる額が少ない
金融商品保有数が少ない
金融商品にも細かく分けると様々な分類がされていきます。
実際は、上記から更に銘柄ごとに枝分かれしていきます。
種類別に分けて管理したくなってくるのが人間の性です。
逆に1商品にずっと積立投資し続ける場合などは、管理も煩雑じゃないし複数の証券口座を持つ理由があまりなくなるね。
総資産が少ない
そるとちゃんが先ほど言ってくれたように、「総資産が少ない」場合についても証券会社を分ける必要性はあまり感じないだろうね。
証券会社の「分別管理義務」は1,000万円が上限のため、1,000万円以下の場合は資産保全の観点から見ると使い分ける意味はあまりないんだね。
「分別管理義務」についてはパパが後述してくれていますので、必ずチェックしておきましょう。
投資できる額が少ない
年間の投資額が少額なのに、わざわざ証券会社を使い分ける意味は薄いです。
逆に管理が煩雑になっちゃって、大変になりそうだよね。
その割に合計しても金額が少ないとなったら、気落ちしちゃいそうだから逆にまとめて管理した方が良さそうだね。
例外としては1株ずつコツコツ投資していて、「日本株」と「米国株」で分けて管理したい場合などは分けてもいいかもしれないです。
以上より、下記のような方が使い分けを検討し始める目安になるかと考えます。
投資を始めたばかりで証券口座をいくつも開設するのはあまり意味をなさないです。
ひとまずパパも開設している「SBI証券」か「楽天証券」のどちらかで開設してコツコツやっていくことから初めてみましょう♪
証券口座を複数持つメリット
- 管理がしやすくなる
- リスク分散になる
- お得に使いこなせる
管理がしやすくなる
証券口座を複数持つメリットとして、最初にあげられるのは「管理面」です。
これは使い方にもよりますが、特に「コアサテライト戦略」を取っている人は分けると非常に見やすくなります。
わたしも可能な限り「コア」はSBIで「サテライト」は楽天という考え方で振り分けて管理しています。
リスク分散になる
金融資産が1,000万円を超えたら必ず知っておきたいのが「分別管理義務」です。
分別管理義務についてざっくり説明すると下記の通りです。
- 日本の証券会社には二重のセーフティネットがある
- 第一として、証券会社の資産は「分別管理」が金融商品取引法で義務付けられているため、基本的に何かあっても預けている資産は返還される
- 第二として、「分別管理」が出来ていなくて証券会社が倒産した場合、顧客の資産は1,000万円まで保護される
へー!
こんな義務が証券会社にはあったんだね。
ただ、1,000万円までしか保護されないんだね…
資産が数千万円レベルになったら、分散しておかないとこわいね…
ママの言う通りで、やっぱり1,000万円を超えてきた後の資産のリスク分散はある程度大事になってくると思ってるよ。
分別管理義務の要旨は、下記の2点です。
非常に強く守られている一方で、サイバーテロや会社の倒産など、何があるかわからないのが金融の世界です。
「そんなこと知らなかった!自分は1億預けていたのに1,000万円しか返ってこないなんてありえない!」なんて事にならないように、「分別管理」の考え方は各証券会社のホームページでしっかり目を通しておきましょう。
「分散」は投資の鉄則ですが、それは証券会社にも言えることです。
お得に使いこなせる
証券会社毎に使える枠が決まっている制度などは、二刀流の方がお得に使いこなせます。
例えばクレジットカードで投資信託の購入が出来て、ポイントが還元される「クレカ積立」などが対象になります。
各社ともクレカ積立の整備が進んだ現在は、下記のようにクレジットカードを用いて投資信託積立が可能です。
- 投資上限額は50,000円/月
- ポイント還元率1%(最大500ポイント)
※三井住友NLカードゴールド利用の場合
- ポイントは「Tポイント」「Vポイント」として利用可能
- 投資上限額は100,000円/月(楽天キャッシュ利用も含む場合)
- ポイント還元率0.5%(最大250ポイント)
※楽天カード利用の場合
- ポイントは「楽天ポイント」として利用可能
- 投資上限額は50,000円/月
- ポイント還元率1.1%(最大550ポイント)
- ポイントは「Tポイント」として利用可能
クレカ積立だけで考えたら「マネックス証券」が1番ポイント還元率が高いんだね。
そうなんだよ、どうせ長期投資で積み立てるならポイント還元があった方が嬉しいよね。
パパも3社に分散して投資信託を積み立てているよ。
パパは全てのポイントを「再投資」しているから、月間で1,400円分はタダで再投資出来ているようなものだと言って喜んでいます。
上記のように「上限が決まっているお得な制度は出来る限り使い倒せる」というのは大きなメリットになります。

おすすめ証券口座使い分け例
ここからはパパのおすすめの証券口座「使い分け」一例を紹介するよ♪
- 投資信託(SBI・V・全米株式orS&P500)
- 高配当ETF(VYM/HDV/SPYD)※自動買付
- 高配当個別株式
- その他個別株式
- 投資信託(S&P500)※クレカ積立
- 投資信託(S&P500)※クレカ積立
月間の積立金額が5万円を超える場合は、上記のようにクレカ積立も併用した方がお得です。
ラップアップ
今回は「証券口座を複数持った方が良い場合」について考察していきました。
使い分けに悩んでいる方の参考になれば幸いです。
最後に一言。
クレカで積み立てているだけでポイントがもらえる、お得な時代になりました。
ぜひ活用してみてください。
それではまた!